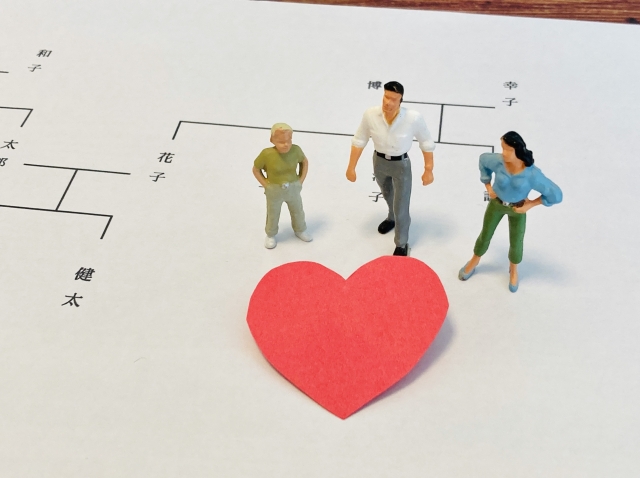贈与税と相続税について知りたい人に向けて、生前贈与をした方がいいケースや贈与でも税金がかからないケースについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
贈与税とは?
贈与税は、贈与によって受け取った財産に対して課せられる税金です。
贈与には、贈与者が贈与した場合や、相続によって受け取った場合などがあり、どちらの場合も贈与税が課せられる可能性があります。
贈与税の税率は国によって異なりますが、通常は贈与金額に対して一定の税率が適用されます。
また、贈与税の非課税額もあり、これを超える分だけ贈与税が課せられます。
贈与税の適用対象や非課税額は国によって異なりますので、確認することが必要です。
贈与税がかかる人
贈与税は、贈与を受ける人に課せられる税金です。贈与を受ける側が課税対象です。
贈与を受ける人は、贈与を受けることで所得を得るため、税金が課せられます。
ただし、贈与税には、所得を得ることによって課税される贈与税と、贈与を受けること自体によって課税される相続税があります。
贈与税は、贈与を受けることによって得られる所得に対して課せられるものです。
贈与税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1500万円超3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の非課税枠
贈与税の非課税枠は、一定の金額までの贈与に対して税金が課せられない限度額のことです。
また、非課税枠は贈与人ごとに設定されており、1人から複数人に贈与する場合でも、非課税枠は個人ごとに適用されます。
非課税枠は年々変更されることがありますので、最新の情報は税務署や司法書士など専門家にお問い合わせください。
贈与税は、年間110万円まで非課税になります。
相続税とは?
相続税は、死亡時に遺産を受け継いだ際に課せられる税金です。
遺産には、不動産、現金、株式、宝石など財産が含まれます。
相続税の税率は国によって異なりますが、通常は相続された財産の評価額に対して一定の税率が適用されます。
また、相続税の非課税額もあり、これを超える分だけ相続税が課せられます。
相続税の適用対象や非課税額は国によって異なりますので、確認することが必要です。
相続税は、相続人によって異なります。
たとえば、配偶者や親族などに対しては特別な非課税枠が設定されていることがあります。
相続税対策として、生前贈与を行うこともできます。
相続税がかかる人
国税庁によると、相続税がかかる人は以下の通りです。
| 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。 |
【基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】の算式で計算します。
- 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人
- 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
- 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
- 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。)
- 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)
- 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人
相続税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の非課税枠
相続税の非課税枠は、基礎控除額が【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】で決められることから、相続人の数によって非課税枠は大きく変化します。
例えば、相続人が1人の場合は3,600万円までが非課税枠です。
相続人が10人いる場合は、9,000万円まで非課税になります。
生前贈与をした方がいいケースとは?
生前贈与をした方がいいケースは、以下のようなケースです。
- 贈与する人が若いケース
- 収益不動産を持っているケース
- 特定の人に贈与したいケース
贈与する人が若いケース
生前贈与をした方が良いケースの一つに、贈与する人が若いケースが挙げられます。
生前贈与は年間110万円まで非課税で贈与することができます。そして、非課税期間には制限がありません。
そのため30歳から亡くなる80歳まで50年間自分の子供や兄弟、親などに生前贈与をすることができれば、110万円×50年で5500万円まで非課税で相続することができます。
また、生前贈与は贈与する対象は限定されていないので複数人に110万円ずつ贈与することで非課税枠を拡大させることも可能です。
このように、贈与する人が若い場合は贈与できる期間が長くなるので、必然的に非課税期間も長くなり、贈与を有利に進められる可能性が高いです。
そのため、贈与する人が若い場合は、生前贈与を早めに行った方が有利になりやすいでしょう。
収益不動産を持っているケース
生前贈与をした方が良いケースの一つに、収益不動産を持っているケースが挙げられます。
収益不動産を生前贈与することで、被相続人が不動産を所有し得ていた家賃収入を現預金で相続する場合と比較して相続税額を抑えることが可能です。
また、不動産は現金や有価証券で資産を保有している場合に比べて、評価額が低くなるのも特徴です。
特定の人に贈与したいケース
生前贈与をした方が良いケースの一つに、特定の人に対して贈与したいケースが挙げられます。
特定の人に対して贈与する場合、遺言書を作成し自分の意思に基づいて相続をすることが考えられます。
その場合、相続人として指定された人と法定相続人の間でトラブルが発生する可能性が考えられます。
一方で生前贈与をすると被相続人となる人が生きているうちに自分の意思で自分の遺産を贈与することが可能です。
また、贈与する対象は法定相続人だけではなく自分が指定した人物、誰に対しても贈与することができます。
そのため、特定の人に対して贈与したいと思っている場合は、年間110万円まで非課税で贈与できる生前贈与を利用するケースも多いです。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、相続時に相続人に対して贈与を行った場合に、贈与税を適用する代わりに相続税を課する制度です。
これにより、贈与の税額よりも相続税の税額が小さい場合には、相続時精算課税制度を利用することで、税金の節税効果を得ることができます。
この制度は、贈与者が60歳以上の両親や祖父母で、受贈者が20歳以上の法定相続人である場合に適用されます。
ただし、非課税限度額が設定されており、それを超える場合には贈与税が課せられます。
また、特例がある場合には利用できないことや、不動産取得税や暦年課税の恩恵を受けられないこともありますので、相続税対策として最適な方法を選ぶためには、専門家に相談することが重要です。
贈与でも税金がかからないケースとは?
贈与でも税金がかからないケースは、以下のような場合です。
- 住宅取得資金等贈与
- 教育資金贈与
- 結婚・子育て資金贈与
住宅取得資金等贈与
住宅取得資金等贈与とは、受贈者が住宅を購入するための資金を贈与することを指します。
購入費、建築費、改装費などが含まれます。
贈与税の非課税額が設定されており、それを超える場合には贈与税が課せられます。
住宅取得資金等贈与は、受贈者が住宅を所有することができるよう支援するものです。
教育資金贈与
教育資金贈与とは、受贈者が教育を受けるための資金を贈与することを指します。
大学や専門学校の学費、留学費、教材費などが含まれます。
受贈者が学生である場合に限られ、贈与税の非課税額が設定されており、それを超える場合には贈与税が課せられます。
教育資金贈与は、受贈者が教育を受けることができるよう支援するものです。
結婚・子育て資金贈与
結婚・子育て資金贈与とは、受贈者が結婚や子育てをするための資金を贈与することを指します。
結婚式の費用、新婚旅行費、出産準備費などが含まれます。
受贈者が結婚する直前や出産する直前の場合に限られ、贈与税の非課税額が設定されており、それを超える場合には贈与税が課せられます。
結婚・子育て資金贈与は、受贈者が結婚や子育てをすることができるよう支援するものです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。