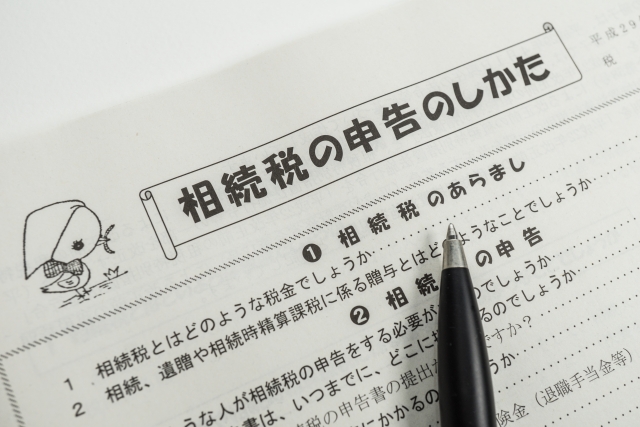税務署から「相続税のお知らせ」が来た場合の対処法について知りたい人に向けて、この記事では「相続税のお知らせ」が来た場合の対処法や「相続税のお知らせ」が来た際には税理士に相談すべき理由も詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
「相続税のお知らせ」とは?
税務署から送られてくる「相続税のお知らせ」とは、亡くなった方の遺産相続において相続税が発生しそうなご家庭に対して送付しているものです。
通常であれば、それなりの資産を持っている方が亡くなった際に、税務署がそれらの資産を把握した上で相続税が発生しそうという場合にのみ送っており、相続税が基礎控除額を下回る場合は送られてくることがありません。
そのため「相続税のお知らせ」が送られてくる時点で相続税が発生する可能性が高いと考えるのが一般的でしょう。
そして「相続税のお知らせ」が送られてくるのは、資産を持っていた方が亡くなった半年から8ヶ月後です。
通常、相続税の納付期限は亡くなった日から10ヶ月後と設定されているので、「相続税のお知らせ」が来た時点では既に納付までの期限が短くなっているというのも大きな特徴です。
また「相続税のお知らせ」が来るということは、税務署がそもそも亡くなった方の資産を把握しており、相続税が発生する可能性が高い事を把握しているということでもあります。
そのような背景から「相続税のお知らせ」が来ているにもかかわらず相続税の申告がされていないと税務調査の対象になる可能性が高く、場合によっては追徴課税が課される場合もあります。
そのため「相続税のお知らせ」が来た時点で何かしら対応が必要になるというのは理解しておくといいでしょう。
税務署から「相続税のお知らせ」が来た際は税理士に相談すべき理由とは?
税務署から「相続税のお知らせ」が来た際は税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。
- 申告期限までの猶予が短い場合が多い
- スムーズに納税までできる
- 専門家のアドバイスをもとに相続税の申告ができる
申告期限までの猶予が短い場合が多い
税務署から「相続税のお知らせ」が来た際に税理士に相談すべき理由の一つに、申告期限までの猶予が短い場合が多いということが挙げられます。
税務署から「相続税のお知らせ」が来る時点ですでに亡くなってから半年から8ヶ月経っていることが多いです。
通常、相続税は亡くなってから10ヶ月以内に納付しなくてはいけません。
そのような背景から「相続税のお知らせ」が来てから相続税の準備をするのであれば納付期限に間に合わない可能性も非常に高いです。
そして、相続の作業を税理士ではなく素人の個人が行う場合、納付期限に間に合わない可能性がさらに高まります。
そのため、税務署から「相続税のお知らせ」が来た時点で、税理士に相談をしてどのような対応すればいいのかを相談すると良いでしょう。
スムーズに納税までできる
税務署から「相続税のお知らせ」が来た際に税理士に相談すべき理由の一つに、スムーズに納税までできるということが挙げられます。
「相続税のお知らせ」が来た時点で納付までの期限が短いためスムーズに納付まですることが求められるだけではなく、「相続税のお知らせ」が来るということはそれなりの資産を持っているご家庭であるということが想定されます。
このようなご家庭の場合、土地や不動産、非上場株式など様々な資産を持っていることが想定され、現預金のみの相続ではない可能性が非常に高いです。
このような場合、土地の評価や非上場株式の評価など様々な面で専門的な業務が必要になってきます。
税理士に専門的な業務を代行してもらうことで、スムーズにそして一貫して納税まで行ってもらえるので、相続人は自分の時間を使うことなくスムーズに納税できるのも大きなメリットです。
専門家のアドバイスをもとに相続税の申告ができる
税務署から「相続税のお知らせ」が来た際に税理士に相談すべき理由の一つに、専門家のアドバイスをもとに相続税の申告ができるということが挙げられます。
「相続税のお知らせ」がくる時点で相続税の申告が必要になる可能性が高いです。
このような場合にどのように相続税を申告すればいいのか、また相続税をなるべく小さくするためにどのような策が考えられるのかなどを含め、専門家の立場から税理士にアドバイスをもらえるというのは、税理士に相談するメリットの一つでしょう。
一方で、相続専門の税理士でない場合「相続税のお知らせ」が来た際の対処法やどのようにしたら相続税を減らすことができるのかなどのノウハウを持っていないことも多いです。
そのような背景から「相続税のお知らせ」が来た際にはなるべく相続専門の税理士に相談すると良いでしょう。
税務署が定義する「相続人」とは?
遺言書などがない場合、相続人は税務署が定義する相続人になります。
税務署が定義する相続人とは民法に沿った相続人のことで、以下のように決められています。
②次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
【第1順位】被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
【第3順位】 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
税務署が定義する「相続される資産」とは?
税務署が定義する「相続される資産」は、以下の4つです。
- 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
- みなし相続財産
- 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
- 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
税務署が定義する相続される資産の中には、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産が挙げられます。
一般的な家庭の場合、被相続人が亡くなった時点で所有されている財産が、遺産のすべてとなることが多いです。
税務署によると、被相続人が亡くなった時点においての所有していた財産は以下のように定義されています。
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
被相続人が亡くなった時点において所有していた財産を算出する上でポイントとなるのが、家族名義であっても被相続人の財産であれば、被相続人の財産として課税対象となるということです。
つまり、名義だけ家族のものになっていても被相続人が保有している財産であれば、それらは相続の対象になり、課税の対象にもなるということです。
また、海外不動産や株式に関しても同様に被相続人の名義であれば課税対象になるのでそれらも含め価値を評価しなくてはいけません。
みなし相続財産
税務署が定義する相続財産の中には、みなし相続財産が挙げられます。
みなし相続財産とは以下のように定義されています
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額※までは非課税となります。
税務署が定義するみなし相続財産の中にも記載されているように、みなし相続財産は一定の金額が非課税となります。
非課税となる金額は500万円×法定相続人の数です。
そのため、法定相続人が10人いる場合は5,000万円までが非課税の対象になり、被相続人の死亡時に支払われる生命保険や退職金などの合計が5000万を超えていない場合は、みなし相続財産の課税対象分は0と計算されます。
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
税務署が定義する相続財産の中には、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産も挙げられます。
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は税務署によると以下のように定義されています。
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
また、相続時精算課税適用財産制度は以下のような制度のことです。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
税務署が定義する相続財産の中には、被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産が挙げられます。
被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産は、以下のように定義されています。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続税の相談は税務署ではなく税理士の方がおすすめの理由
相続税の相談は税務署ではなく税理士の方がおすすめの理由は、以下の3つです。
- 土日でも相談できる
- 税務調査への帯同も依頼できる
- 寄り添ったアドバイスをくれる
土日でも相談できる
相続税の相談は税務署ではなく税理士の方がおすすめな理由の一つに、土日でも相談できるということが挙げられます。
土日は税務署が空いていないので仕事を平日にしている人の場合、税務署に相談をしに行くということが物理的に難しいことも多いです。
その点、税理士であれば土日であっても営業していることが多いので、平日の日中に仕事をしている人でも相続税の相談をすることができます。
税務調査への帯同も依頼できる
相続税の相談は税務署ではなく税理士の方がおすすめな理由の一つに、税務調査への対応も依頼できるということが挙げられます。
税務調査とは、申告漏れなどがあった場合に資産などを含め相続人の資産を調査することを指します。
これらの調査をする際には、相続人が調査の見守りをすることも可能ですが、税理士に代わりに見守りをお願いすることも可能です。
そして、税理士に税務調査の見守りを依頼したほうが税金関連の話については理解してる分、スムーズに行くことも多いです。
寄り添ったアドバイスをくれる
相続税の相談は税務署ではなく税理士の方がおすすめな理由の一つに、税理士の方が寄り添ったアドバイスをくれるということが挙げられます。
税務署はあくまでも公的に決められたルールから逸脱するものは提案してくれず、税収を減らすような提案も基本的にはしてくれません。
一方で、税理士の場合、税務署では提案することができないような節税策について提案してもらうことも可能です。
このように、親身になってコンサルティングを含め相続人に寄り添ってアドバイスをくれるのも税理士に相続税の相談をするメリットのひとつです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。