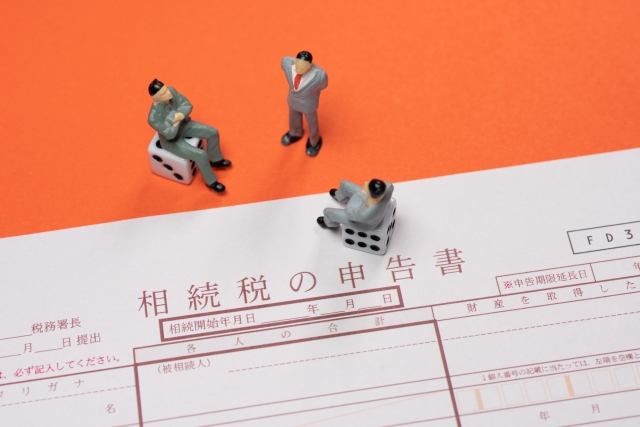相続税を減らせる相続税対策について知りたい人に向けて、相続税を減らせる相続税対策や専門家に相続税対策を相談するメリットを紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続税を減らせる相続税対策とは?
相続税を減らせる相続税対策には、以下のものが挙げられます。
- 生前贈与を行う
- 生命保険金の非課税枠を利用する
- 養子縁組で法定相続人を増やす
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用する
- 相続時精算課税制度を利用する
- 収益不動産を贈与する
生前贈与を行う
相続税対策として生前贈与を行う主な理由は、相続税負担を軽減することができるからです。
生前贈与とは、相続予定財産のうち、現在の所有者である相続人が、死後に相続する予定の財産の一部を、生前に贈与することをいいます。
生前贈与によって、相続財産が減少するため、相続税の課税対象となる財産の価値が下がります。
また、贈与者自身が生前に贈与することで、相続人の負担を軽減することができます。
生前贈与の利点としては、次のようなものが挙げられます。
- 相続税負担軽減:生前贈与によって、相続予定財産の一部を相続人に贈与することで、相続税の負担を軽減することができます。
- 節税効果:生前贈与によって、贈与税がかかる場合がありますが、相続税に比べて税率が低いため、贈与税が節税につながる場合があります。
- 贈与者自身の負担軽減:生前贈与によって、相続人が財産を受け取るための手続きや手数料が軽減されるため、贈与者自身の負担を軽減することができます。
ただし、生前贈与を行う場合には、注意点もあります。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 贈与税の負担:生前贈与によっては、贈与税がかかる場合があります。贈与税の計算方法や節税方法については、税理士や弁護士に相談する必要があります。
- 贈与後の財産管理:生前贈与によって、相続人が贈与された財産を管理する必要があります。相続人に十分な能力がない場合には、信託などの方法を用いて、財産管理を行う必要があります。
- 相続人間の不和の可能性:生前贈与によって、相続人間の間で不和が生じる可能性があります。相続人間の関係性や家族構成などを考慮して、生前贈与を行う。
生命保険金の非課税枠を利用する
国税庁によると、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となるとされています。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
具体的な非課税額は、【500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額】です。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
養子縁組で法定相続人を増やす
養子縁組で法定相続人を増やすことで相続税対策をすることも可能です。
養子縁組によって、養子と養親との親子関係が法的に認められます。
これにより、養子には、養親の扶養義務が発生し、養親の財産に対する相続権も認められます。
また、相続人が多くなると、相続税の課税対象となる財産を分散させることができ、相続税負担を軽減することができます。
養子縁組によって、法定相続人の数が増えることで、相続人一人当たりの非課税枠が増えるため、相続税の負担が軽くなることがあります。
ただし、養子縁組を行う際には実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までしか養子縁組をして法定相続人として認められません。
そのため、養子縁組をして法定相続人をする際には、専門家に相談の上進めるようにしましょう。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用する
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、国税庁によると以下の通りです。
| 平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用することで、非課税枠を増やせるのが大きな魅力です。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税の制度とは、国税庁によると以下の通りです。
| 原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。 |
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
そして、相続時精算課税制度を選択することで、2,500万円の控除を使うことができます。
暦年贈与の控除は年間で110万円までしか適用されませんので、2,500万円を非課税で贈与できるというのは大きなメリットでしょう。
収益不動産を贈与する
日本において収益不動産が相続税対策に有効な理由は以下の通りです。
| 評価額が安定している:収益不動産は、賃料収入があるため、その収益が基になって評価されるため、評価額が比較的安定しています。そのため、相続税の課税対象となる資産としては、評価額が高い株式や現金よりも、収益不動産の方が相続税負担を軽減することができます。 減価償却資産として扱われる:収益不動産は、減価償却資産として扱われます。つまり、不動産の価値を減価償却費用として経費に計上することができるため、収益不動産を所有することによって、税金を節約することができます。相続税も、評価額から減価償却費用を差し引いた金額が課税対象となるため、相続税負担を軽減することができます。 相続税非課税枠が大きい:日本の相続税制度では、相続人ごとに一定の非課税枠が設けられています。収益不動産は、評価額から減価償却費用を差し引いた金額が相続税負担対象となるため、その差額が相続人ごとの非課税枠を超えない場合は、相続税が課税されないことがあります。 |
専門家に相続税対策を相談するメリットとは?
専門家に相続税対策を相談するメリットは、以下の3つです。
- 専門的なアドバイスをもらえる
- 合法の範囲内で最適な提案をもらえる
- 各種作業を代行してもらえる
専門的なアドバイスをもらえる
専門家に相続税対策を相談するメリットの一つに、専門的なアドバイスをもらえることが挙げられます。
相続税対策では、生前だからできる相続税対策もあります。
例えば生きているうちに生前贈与を行えば、相続人が遺産を受け取る際に支払う相続税の金額を抑えることも可能です。
このような専門的なアドバイスをもらえるというのは大きな魅力でしょう。
また、相続税申告の際には使える控除・特例も多くあります。
このような使える控除・特例を専門家に提案してもらえるのも大きな魅力です。
合法の範囲内で最適な提案をもらえる
専門家に相続税対策を相談するメリットの一つに、合法の範囲内で最適な提案がもらえることが挙げられます。
相続税対策においてはややグレーな方法があるのも事実です。
しかしこれらの方法を取ってしまうと相続税申告の段階で認められない可能性もあります。
例えば、不動産を購入し評価額を抑える方法もありますが、方法を間違えてしまうと不動産購入そのものが否定されてしまう可能性も考えられます。
このような背景から合法の範囲内で最適な提案をもらえるというのが、税理士などの専門家に相続税対策を相談するメリットのひとつです。
各種作業を代行してもらえる
専門家に相続税対策を相談するメリットの一つに、各種作業を代行してもらえることが挙げられます。
相続税申告において、税理士に相談をすれば税理士が代わりに相続税申告書の作成、相続税申告を行ってくれます。
このように各種作業を代行してもらえるというのも専門家に依頼するメリットの一つでしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。