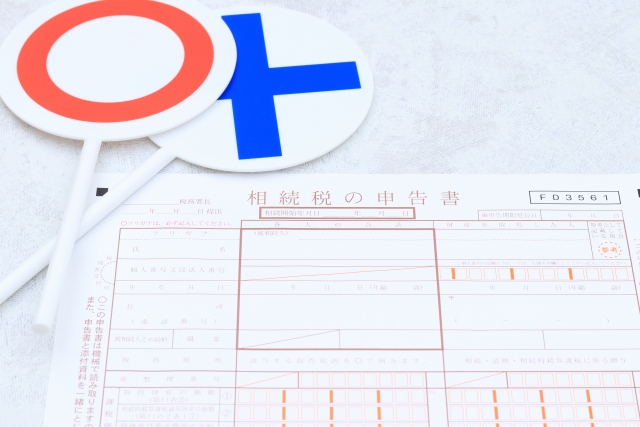相続時の税金の基礎控除について知りたい人に向けて、この記事では相続時の税金の基礎控除や相続税の基礎控除額の計算方法、相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続税の基礎控除額の計算方法
国税庁によると、相続税の納付金額は以下のように計算するとされています。
- 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】 - 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
a.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
b.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。 - 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】 - 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】 - 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】
相続税の基礎控除額に関係する法定相続人とは?
相続税の基礎控除額に関係する法定相続人は、法律で決められており、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の遺産相続の順位は国税庁より以下のように記載されています。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続人となる子供がすでに亡くなっている場合は、孫が祖父母も遺産を相続することが可能です。
孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥や姪が相続することになります。
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点は、以下の3つです。
- 養子の数には限りがある
- 法定相続人との間で揉める可能性がある
- 手続きに時間がかかる可能性がある
養子の数には限りがある
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点の一つに、 養子を迎え入れる際には養子の数に制限があるということが挙げられます。
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組を何人ともすることができれば、その分、国としては相続税の納付金額が抑えられてしまう事にもなります。
このような背景から相続税法では養子縁組ができる数が決まっています。
子供がいない場合は2人まで、子供がいる場合は1人までしか養子縁組をすることができません。
そのため、養子縁組を何十人としても相続税の基礎控除額を増やすことはできないということは覚えておきましょう。
ただし、国税庁によると以下の場合は、全て養子を法定相続人に数えることができるとされます。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属
なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
法定相続人との間で揉める可能性がある
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点の一つに、 法定相続人と養子縁組をした養子が揉める可能性があるということが挙げられます。
養子縁組をする際には、被相続人となる人が事前に法定相続人となる人に対して養子縁組をする旨を伝えておくことが重要と言えるでしょう。
法律的な観点から言うと法定相続人に対して養子縁組をしていることを周知する義務はありません。
一方で被相続人が亡くなった後に法定相続人と養子縁組をした養子の間でトラブルになる可能性は非常に高いのも事実です。
このような背景から法定相続人との間で揉める可能性をなるべく低くするためにも、被相続人となる人が生きているうちに養子縁組をする旨を法定相続人に伝えておくことが重要と言えるでしょう。
それだけではなく、遺言書を作成してどのように遺産配分するのかなども事前に決めておけるとトラブルになる可能性を減らすことができます。
手続きに時間がかかる可能性がある
相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をする際の注意点の一つに、 養子縁組をすること自体に手続きの時間がかかってしまう可能性があるということが挙げられます。
養子縁組をする際には市区町村に届け出をした上で、必要な書類を記載し、養子縁組をする必要が求められます。
そのため、手続きに時間がかかってしまい被相続人となる人が亡くなる直前に、これらの手続きを行うと結果的に被相続人となる人が亡くなる前までに養子縁組ができないという可能性も考えられるでしょう。
養子縁組をする際の届出場所や必要な書類は以下の通りです。
◆届出場所:養親・養子の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口
◆必要な書類
- 養子縁組届(成年者証人2名の署名が必要です。)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地以外に届出する場合のみ)
- 配偶者の同意書
- 家庭裁判所の許可審判書の謄本(注意2)
相続税は税理士に相談すべき理由とは?
相続税を税理士に相談すべき理由は、以下の3つです。
- 相続税の計算を任せられる
- 正確に相続税の計算ができる
- 相続税申告に使う時間を減らせる
相続税の計算を任せられる
相続税は税理士に相談すべき理由の一つに、相続税の計算を全て税理士に任せられるということが挙げられます。
相続税計算をする際に財産が多いと、それらの財産を評価し、かつ必要な控除や使える特例などを調査した上で相続税を算出しなくてはいけません。
これらの調査は時間がかかるのも事実なので、相続税の計算を全て税理士に任せられるというのは大きなメリットでしょう。
正確に相続税の計算ができる
相続税は税理士に相談すべき理由の一つに、正確に相続税の計算ができるということが挙げられます。
相続税申告の際に申告漏れや申告ミスが発生するとそれに伴いペナルティが科せられる可能性もあります。
それだけではなく税務調査の対象になる可能性も考えられるでしょう。
このようなリスクを抑えるために、正確に相続税の計算ができる税理士に相続税の算出を依頼するのがおすすめです。
特に、不動産や株券などの資産が多い場合、相続税計算が複雑になりやすく、かつ計算ミスが発生しやすくなります。
そのような背景から現預金だけを相続するのではなくそのほかの資産も同時に相続する場合は、税理士に依頼した方が安全と言えるでしょう。
相続税申告に使う時間を減らせる
相続税は税理士に相談すべき理由の一つに、相続税申告に使う時間を減らせるということが挙げられます。
相続税申告に慣れている税理士に相続税申告を一括で依頼することで、相続人は相続税申告に使う時間を減らすことができ、スムーズに相続できるようになります。
特に、税務について知識のない素人の場合、相続税申告をどのようにすればいいのかがわからず、申告方法を調べるために時間を使ってしまう可能性も考えられます。
このような背景からも相続時申告をスムーズにでき、かつ自分で深く調査することなく相続ができるのは大きなメリットでしょう。
相続時によくあるミスとは?
相続時によくあるミスは、以下の2つです。
- 課税対象にも関わらず無申告
- 本来の納付金額以上の金額を納付
課税対象にも関わらず無申告
相続時によくあるミスの一つに、相続税の申告対象にもかかわらず相続税を申告しない無申告状態であるということが挙げられます。
現金だけではなく、不動産などの資産を相続した際に、それらの資産評価額の算出方法が正式なものとは異なることで、結果的に自分たちが相続税の申告対象ではないと判断してしまい相続税の申告をしないというケースがあります。
相続税には、基礎控除額が設けられているので、基礎控除額内であれば相続税申告をする必要がありません。
一方で、基礎控除額を超える場合は相続税の申告をしなくてはならず、評価額と基礎控除額の関係でトラブルが発生する可能性が高いです。
本来の納付金額以上の金額を納付
相続時によくあるミスの一つに、本来の納付金額以上の金額を納付してしまうということが挙げられます。
本来ならば特例などを使って、相続税の評価額を抑えられたにも関わらず、特例などを適用しなかったことで本来払わなくてはいけない金額以上の相続税を支払ってしまう可能性があります。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。