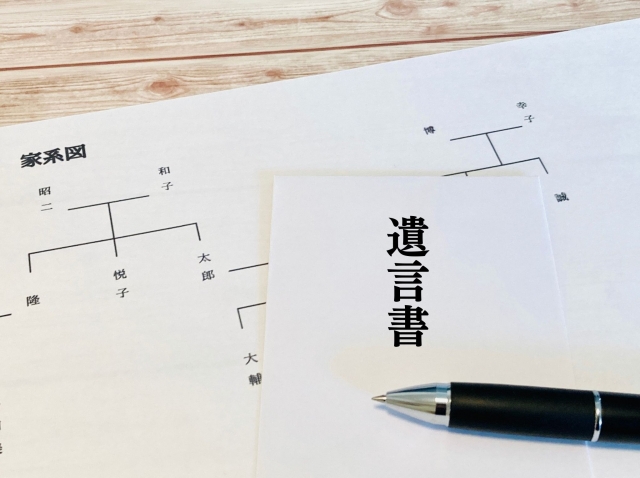相続の順位を知りたい人に向けて、この記事では相続の順位や遺言書で相続人を決めるメリットを紹介します。
それでは、見ていきましょう。
法定相続人の相続順位
法定相続人の相続順位は、以下の通りです。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
遺言書がない場合、法定相続人になれるのは配偶者と血族のみです。また、法定相続人には順位があり、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。
また、法定相続人となる子供がすでに亡くなっている場合は、孫が祖父母も遺産を相続することが可能です。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥や姪が相続することになります。
相続時に発生するトラブルとは?
相続時に発生するトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
- 不動産など分割できない遺産の分割方法
- 法定相続人間での仲が悪く意思疎通ができない
- 遠方に住んでいる相続人がおりスムーズに相続ができない
- 認知症などを発症し分割協議ができない
- 介護などを一人が担っていたことでの分割方法への不満
不動産など分割できない遺産の分割方法
相続時に発生するトラブルの一つに、不動産など分割できない遺産の分割方法で揉めるということが挙げられます。
不動産の場合、すぐに現金化することで相場よりも低い金額で売却しなくてはいけないケースもあります。
不動産のような有形資産の場合、売却等で有形資産を現金化して、現金を相続人間で分割することが多いです。
しかし、相続した不動産に相続人の一人が住んでいる場合は、現金化するのではなく相続人の1人が当該の不動産を相続するというケースもあります。
この場合どのように価値判断をするのかで揉めるケースも多く、遺産の取り分が多い少ないで揉めるケースもあります。
法定相続人間での仲が悪く意思疎通ができない
相続時に発生するトラブルの一つに、法定相続人同士の仲が悪く意思疎通ができていないということが挙げられます。
法定相続人同士の仲が悪い場合、相続時に上手くコミュニケーションができておらず、結果的にスムーズに法定相続人同士の会話が進まないケースも多いです。
遺産分割では、全ての法定相続人の同意が必要になり、全員の同意が取れていない状態では相続することができません。
そのような背景から法定相続人同士の仲が悪い場合や誰かが言ったことに対して他の誰かが真っ向否定する状態の場合は、遺産分割協議自体が進まないというケースもあります。
この場合、遺産分割調停などに持ち込まれることもあり、遺産分割までの期間が長くなってしまうでしょう。
遠方に住んでいる相続人がおりスムーズに相続ができない
相続時に発生するトラブルの一つに、遠方に住んでいる相続人がおりスムーズに相続できないということが挙げられます。
日本国内ではなく海外に住んでいる相続人がいる場合、それらの相続人と意思疎通をした上で相続の割合を決定しなくてはいけません。
今は、WEBなどを通して気軽に海外にいる人ともコミュニケーションを取ることができますが、そもそも遠方に住んでおり連絡先を知らない、どこにいるのかわからない相続人がいる場合、遺産分割協議自体がまとまらず遺産分割の方法すらまとまらないという事態にもなりかねません。
このような背景から遠方に住んでいる相続人がいる場合は、スムーズに相続ができずトラブルになる可能性もあります。
認知症などを発症し分割協議ができない
相続時に発生するトラブルの一つに、認知症などを発症し遺産分割協議ができないということが挙げられます。
遺産分割協議では、すべての法定相続人が同意することが求められますが、認知症を発症している場合、正常な判断ができず結果的に同意が得られない可能性もあります。
認知症の場合、法定代理人である成年後見人がいなければ、遺産分割協議に法定代理人が参加することが可能ですが、法定代理人の選出手続きを行っていなかった場合、法定代理人の選出手続きを行うことが必要です。
そのため、認知症の人が法定相続人にいる場合、遺産分割協議に時間がかかる可能性が高いでしょう。
介護などを一人が担っていたことでの分割方法への不満
相続時に発生するトラブルの一つに、相続する法定相続人の一人が被相続人の介護を一人で担っていた場合、そのことに対しての対価として法定相続分以上の遺産相続を要求するケースが挙げられます。
法定相続人同士で遺産分割を行う場合、法定相続分しか基本的には相続することができません。
ただし、遺言書がある場合は、法定相続分に関係なくある特定の相続人が多くの割合の遺産を受け取ることができます。
そのため、被相続人が遺言書を残しておらず、最後まで被相続人のお世話をした人が1人であった場合、相続人に遺産が均等に分割されることに対して不満に思うケースもあります。
実際に、遺産分割のトラブルの中ではこのように誰か一人が献身的に被相続人のお世話をしていたにも関わらず、何も世話をしていなかった他の相続人と同じ遺産をもらうことに納得できないというケースも多いです。
遺言書を書けば相続の順位に関係なく自分の意思で相続人を決められる
遺言書を作成していない場合、被相続人が残した遺産は法定相続人に均等に振り分けられることになります。
一方で、遺言書を書いている場合は、法定相続人や相続順位に関係なく遺言書に記載された相続人が記載された割合で遺産を受け取ることが可能です。
そのため、自分の世話をしてくれた子供に対してより多くの遺産を相続させることもできます。
それだけではなく、法定相続人以外に対しても相続させることが可能なので、内縁の妻など法的には相続権がない人であっても相続人に指定して、遺産を相続させることができます。
遺言書で相続の順位を指定するメリットとは?
遺言書で相続の順位を指定するメリットは、以下の通りです。
- スムーズに相続ができる
- 生前の世話をしてくれた子供に多く遺産を残せる
- 被相続人の意思で相続を決められる
スムーズに相続ができる
遺言書で相続の順位を指定するメリットの一つに、遺言書で相続順位を決めることでスムーズに相続できるということが挙げられます。
被相続人が亡くなったあとに、遺言書がない場合は遺産分割協議を開催した上で、遺産分割協議を行い、法定相続人全員の同意を得ることが必要です。
一方で、相続人の間でどのように遺産分割をするかを検討する際に、遺言書があり事前に相続順位が決められている場合、遺言書に沿った相続をすることになりスムーズに相続することができます。
そのため、相続人も遺産を早い段階で受け取れるというメリットもあります。
生前の世話をしてくれた子供に多く遺産を残せる
遺言書で相続の順位を指定するメリットの一つに、亡くなる前の世話をしてくれた子供に多くの遺産を残せるということが挙げられます。
現状の法律では、同じ子供であれば長男であろうが長女であろうが次男であろうが次女であろうが同じ割合で遺産分割されることになります。
そのため、次女が献身的に被相続人の介護をしていた場合であっても、次女と長男は同じ割合で遺産相続されることになります。
ただし、被相続人が遺言書に世話をしてくれた次女に対して、より多くの遺産を残したい旨を記載すれば、遺言書に従って遺産相続をされることになるので、被相続人の世話を献身的に行った次女に対して、より多くの遺産を残すことも可能です。
被相続人の意思で相続を決められる
遺言書で相続の順位を指定するメリットの一つに、被相続人の意思で遺産相続を決められるということが挙げられます。
通常、相続は被相続人が亡くなった後に行われるものであり、相続で被相続人の意思が反映されることはありません。
ただし、遺言書を作成している場合は遺言書で自分の意思を明確にしておくことで、被相続人の意思を反映した相続をすることが可能です。
例えば、自分と仲が悪い人に対して相続をさせたくないと思っている場合、遺言書にその旨を記載しておくことで遺言書の通りに相続することができます。
ただし、遺言書を作成する場合、遺言書として認められた形式で、かつ認められた方法で作成しないと効力がなくなってしまいます。
そのような背景もあり遺言書を作成する際には、自分だけで作成するのではなく、作成方法を知っている司法書士や弁護士などに依頼する方がいいでしょう。
配偶者に多くの遺産を相続する方法とは?
配偶者に多くの遺産を相続する方法は、以下の通りです。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与を行う
- 配偶者を受取人にして生命保険を契約する
遺言書を作成する
配偶者に多くの資産を相続する方法の一つに、遺言書を作成することが挙げられます。
法定相続人として財産が分けられる場合、配偶者は遺産の総額の1/2を受け取ることになります。
一方で、遺言書を作成し、遺言書で不動産などの特定の財産については配偶者に対して分け与えると記載することが配偶者により多くの遺産相続をすることが可能です。
生前贈与を行う
配偶者に多くの資産を相続する方法の一つに、生前贈与を行うことが挙げられます。
生前贈与は、年間110万円まであれば非課税で行うことができます。
そのため、被相続人が生存しているうちに生前贈与を行うことで、結果的に配偶者に対してより多くの財産を残すことが可能になります。
配偶者を受取人にして生命保険を契約する
配偶者に多くの資産を相続する方法の一つに、配偶者を受取人にして生命保険を契約することが挙げられます。
生命保険を契約し、配偶者を受取人にすることで、遺産相続において以下のようなメリットがあります。
- 遺産の総額を増加させることができる: 生命保険の遺産金は、遺産の総額に加算されるため、配偶者に対する遺産の減少を防ぐことができます。
- 相続税対策になる: 生命保険は、相続税対象から除外されるため、相続税の節税効果があります。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。