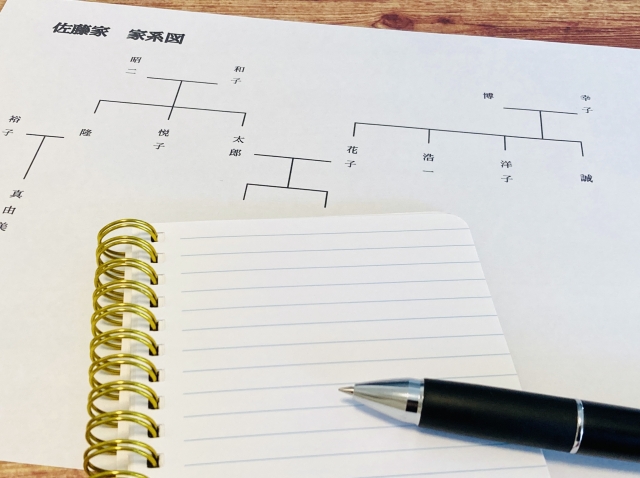家族が死亡した際にすべきことを知りたい人に向けて、この記事では家族が死亡した時にやることや家族が死亡した最初の1週間ですべきこと、ご家族が死亡した際に行う手続きについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
家族が死亡した最初の1週間ですべきこととは?
家族が死亡した最初の1週間ですべきことは、以下の通りです。
- 葬儀社の手配
- 知り合い・親族への連絡
- 死亡診断書の受け取り
- 死亡届の提出
- 葬式
死亡診断書の受け取り
家族が死亡した最初の1週間ですべきことに、死亡診断書の受け取りが挙げられます。
死亡診断書について厚生労働省は、以下のように発表しています。
- 死亡診断書は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものです。したがって、死亡診断書(死体検案書)の作成に当たっては、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入します。
- 我が国の死因統計作成の資料となる。死因統計は国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として役立つとともに、医学研究をはじめとした各分野においても貴重な資料となっています。厚生労働省では、我が国の基幹統計である人口動態統計として公表しています。
死亡診断書は、医師によって記載されるので病院で亡くなった場合は、死亡を宣告した医師が死亡診断書を記載することになります。
死亡届の提出
家族が死亡した最初の1週間ですべきことに、死亡届の提出が挙げられます。
死亡届の概要は以下の通りです。
対象者:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
提出時期:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
提出方法:届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
手数料:不要
死亡届を提出しないと、戸籍上死亡したことにならず相続の際に不利益が発生する可能性もあります。
そのような背景から、死亡届はすぐに提出することはもちろんですが、必ず提出するように意識しておきましょう。
死亡時に必要な手続きとは?
死亡時に必要な手続きは、以下の2つに分けることができます。
- 自治体に対して行う手続き
- 民間業者に対して行う手続き
自治体に対して行う手続き
自治体に対して行う手続きは、以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の提出
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 年金の受給停止
- 国民健康保険の資格喪失届の提出
- 後期高齢者医療の資格喪失届の提出
- 介護保険の資格喪失届の提出
- 国民年金の受給停止
- 住民票の世帯主変更届
- 児童扶養手当認定請求
- 復氏届
- 姻族関係終了届
- 運転免許証の返却
- 遺族年金の受給申請
- 所得税準確定申告
- 相続登記
- 相続税申告
- 高額医療費の請求
民間業者に対して行う手続き
- 電気の解約届
- ガスの解約届
- 水道の解約届
- NHKの解約届
- インターネットの解約届
- 電話の解約届
- 賃貸住宅の解約
- 生命保険金の請求
- 銀行口座の凍結
- 証券の名義変更
- クレジットカードの解約届
ご家族が死亡した際に行う手続きとは?
ご家族が死亡した際に行う手続きとは、以下の通りです。
- 生命保険金の請求手続き
- 高額療養費の還付手続き
- 遺族年金の手続き
生命保険金の請求手続き
ご家族が死亡した際に行う手続きに、生命保険金の請求手続きが挙げられます。
生命保険金の請求手続きでは、生命保険会社によって異なりますが、以下のような情報提供が求められます。
- 証券番号
- 亡くなられた方(被保険者)の氏名
- 亡くなられた日
- 亡くなられた原因(事故や病気など)
- 死亡保険金受取人の氏名と連絡先
- ご連絡いただいた方の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
- 亡くなられる前の入院や手術の有無
生命保険金の請求手続きは、3年以内に行わないと時効になってしまい保険金が支払われないこともあります。
そのため、なるべく早い段階で生命保険金の請求手続きを行うことが必要です。
高額療養費の還付手続き
ご家族が死亡した際に行う手続きに、高額療養費の還付手続きが挙げられます。
高額療養費の還付とは、医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
高額療養費の還付手続きは、亡くなられた方の相続人、または遺言書で指定された受遺者のみとされています。
高額療養費の還付手続きは、申請先は亡くなられた方が加入していた医療保険によって異なり、健康保険の加入者の場合は加入していた健康保険組合で、国民健康保険の場合は自治体です。
遺族年金の手続き
ご家族が死亡した際に行う手続きに、遺族年金の手続きが挙げられます。
遺族年金の概要は、国民年金機構によると以下の通りです。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由とは?
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由は、以下の通りです。
- 相続関連の手続きに時間をかけずに相続できる
- 特例等を適用して相続税を抑えられる可能性がある
- 第三者を入れて相続について考えられる
- 追徴課税の可能性が低くなる
- 財産評価を適正にしてくれる
相続関連の手続きに時間をかけずに相続できる
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由の一つに、相続菅蓮の手続きを時間をかけずにできるということが挙げられます。
相続をする上では被相続人が保有していた資産を、すぐに相続人たちが受け取ることはできません。
被相続人が保有していた資産を遺産分割協議書を作成した上で、どのように相続をするかを明確にし、相続税の支払い・書類の提出が必要になります。
このような一連の手続きを税理士に依頼する場合、代行してもらうことは可能です。
そのような背景から相続関連の手続きに時間をかけることなく相続ができるというのが大きな特徴でしょう。
また、スムーズに相続できるので相続した不動産や証券などを担保に銀行からお金を借りたり、資産を活かしたビジネスも早く開始できます。
特例等を適用して相続税を抑えられる可能性がある
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由の一つに、特例等を適用して相続税を抑えられる可能性があるということが挙げられます。
相続税には、様々な特例や控除がありそれらの特例や控除を利用することで、相続税の金額を抑えることが可能です。
一方で相続について知らない人、税金について理解してない人の場合、特例や控除について自分が使えるものにも関わらず使いこなせないということもあります。
税務署の場合、これらの特例や控除を積極的に教えてくれるということはありません。
そのような背景から特例を適用して相続税を抑えられる可能性があるというのも、相続税の手続きを税理士に依頼するメリットのひとつです。
第三者を入れて相続について考えられる
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由の一つに、第三者を入れて相続について考えられるということが挙げられます。
相続について親族間だけで考えるのではなく、専門家である税理士を入れて相続について話し合うことで、建設的な話し合いをすることができます。
相続においてはある程度決まった形があり、かつ相続人として法律で決められた人もいます。
このような背景から第三者を入れて相続について話し合いをすることで、より客観的に、そして合理的な話し合いをすることも可能になるでしょう。
そして、専門家である税理士を入れることで税理の専門家として、どのように対処すればいいのかのアドバイスをもらうことも可能です。
追徴課税の可能性が低くなる
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由の一つに、追徴課税の可能性が低くなるということが挙げられます。
以下のように国税庁では定義されています。
財産評価を適正にしてくれる
相続の手続きを税理士に依頼すべき理由の一つに、財産評価を適正に行ってくれるということが挙げられます。
税理士に相続税の依頼をすることで、被相続人が保有していた財産を適正に判断してくれ、それに応じた相続税の支払いで済むようにしてくれます。
相続税を支払う際には、現預金だけではなく土地や非上場株式、その他資産となるもの全て合算して価値判断を行います。
税理士の場合、不動産などの定量的に価値判断が難しい資産について、過去の事例などをもとに資産の評価をしてくれ、かつ納税の際になるべく納税額が低くなるような計算方法を教えてくれることも多いです。
それだけではなく、特例や適用することで被相続人が保有していた財産から算出される相続税を適切に算出してくれるのも大きな特徴でしょう。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。