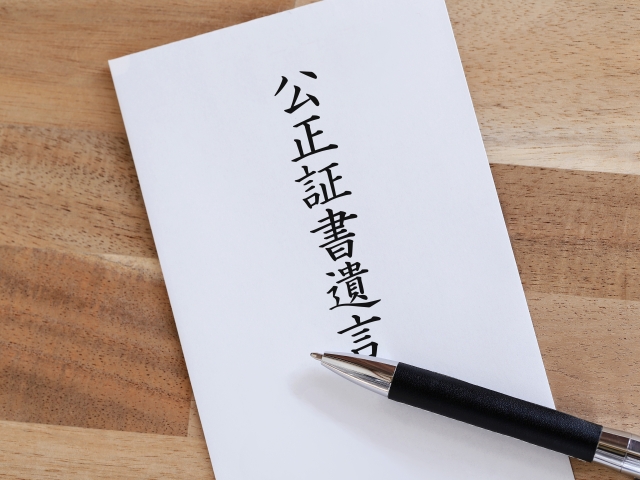公正証書遺言について詳しく知りたい人に向けて、この記事では公正証書遺言のメリット・デメリット、公正証書遺言の作成方法を詳しく紹介します。
それでは見ていきましょう。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名以上の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものです。
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言書作成におけるアドバイスをくれるので、遺言書を作成した経験がない人であっても法的効力を持った遺言書を作成できるというのが大きな特徴になります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、以下の3つです。
- 被相続人の意思を反映できる
- 遺言書を相続人が探しやすい
- 遺言書の信頼性が高い
被相続人の意思を反映できる
公正証書遺言のメリットの一つに、相続人の意思を反映できるということが挙げられます。
公正証書遺言の場合、財産を相続したい被相続人が生きているうちにどのように自分の財産を相続をするかを決めることができます。
そのため、生前に自分の意思を反映した相続プランを立てやすいというのが大きなメリットでしょう。
相続の場合、通常は被相続人が亡くなった後に法定相続人に対して相続され、法定相続人の取り分は機械的に決まっています。
一方で、公正証書遺言のように自分でどの相続人に対してどのくらい相続するかを決めることができれば、その分自由度高くそして自分が世話になった人に対してより手厚く相続をするなどのメリットもあります。
遺言書を相続人が探しやすい
公正証書遺言のメリットの一つに、遺言書を相続人が探しやすいことが挙げられます。
公正証書遺言の場合、遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書に関するデータが一元的に管理されております。
そのため、全国どこで作成されたものであっても検索することができます。
遺言検索は無料ですが、検索・請求できる人は遺言者の生前・死後で異なるので注意しましょう。
遺言者の生前の場合遺言者本人のみしか請求することができず、遺言者の本人確認資料、遺言者の委任状と印鑑証明書、代理人の本人確認資料が必要です。
また、遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。
遺言者の死後は、当該遺言について「法律上の利害関係」のある人のみが検索・請求できます。
ただし、利害関係のある人は相続人だけではなく、被相続人と金銭的なトラブルを抱えていた人なども含まれ、利害関係者が相続人だけではないことに注意しましょう。
請求にあたり必要な書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本や請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料、相続人が請求人である場合はこれを証明する戸籍謄本です。
遺言書の信頼性が高い
公正証書遺言のメリットの一つに、遺言書の信頼性が高いことが挙げられます。
公正証書遺言の場合、偽造ができないこともあり遺言書としての信頼性が非常に高く、遺言書として有効と認められる可能性が非常に高いです。
そのため、遺言書を遺し、そして遺言書通りに相続したい場合は公正証書遺言を利用するのがおすすめでしょう。
ただし、公正証書遺言の場合でも信頼性を担保するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 2人以上の適格な証人がいること
- 遺言書の内容は遺言者が直接伝えたものであること
- 遺言者、証人、公証人の署名捺印があること
- 遺言者の年齢が15歳以上であること
- 遺言の内容が公序良俗に反していないこと
また、公正証書遺言の場合であっても遺言者の認知能力などに問題があると判断された場合は、公正証書遺言が無効になるケースもあります。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、以下の3つです。
- 作成に費用がかかる
- 証人をつける必要がある
- 手続きに時間がかかる
作成に費用がかかる
公正証書遺言のデメリットの一つに、公正証書遺言を作成するのに費用がかかるということが挙げられます。
日本公証人連合によると、公正証書遺言の作成にかかる手数料は以下の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本及び謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付するので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
また、正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
遺言者が、病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、御自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、上記(1)の手数料が50%加算されることがあるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
公正証書遺言の作成費用の概要は、以上でほぼ御説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。
しかし、余り細かくなるので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、御遠慮なくお尋ねください。
証人をつける必要がある
公正証書遺言のデメリットの一つに、証人をつける必要があるということが挙げられます。
公正証書遺言の場合、証人が二人以上必要です。
ただし、証人となる人には必要な資格がなく、誰でも証人になることができます。
また、自分で証人を見つけることができない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
手続きに時間がかかる
公正証書遺言のデメリットの一つに、手続きに時間がかかるということが挙げられます。
公証役場で公正証書遺言を作成すること自体は30分から1時間程度でできます。
しかし、公正証書遺言をどのような内容にするのか、そして弁護士や司法書士と打ち合わせをする場合は、公正証書遺言の作成にかかる打ち合わせの時間も加味しなくてはいけません。
このように、手続きに時間がかかり、作成する前の段階で多くの時間を費やす必要があるというのは大きなデメリットでしょう。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成方法は、日本公証人連合によると以下のように決められています。
| ◆公証人への相談及び依頼 公正証書遺言は、士業者や銀行を通じるなどして、公証人に相談や依頼をすることもできますが、必ずしも士業者や銀行を介する必要はなく、遺言者やその親族等が、公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりするなどして、公証人に直接相談や依頼をしても一向に差し支えありませんし、実際にも、そのような場合が少なくありません。 ◆相続内容のメモ及び必要資料の提出 メール送信、ファックス送信、郵送等により、又は持参して、相続内容のメモ(遺言者がどのような財産を有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、又は遺贈したいと考えているのかなどを記載したメモ)を公証人に御提出ください。 ◆遺言書公正証書の案の作成と修正 公証人は、前記2で提出されたメモ及び必要資料に基づき、遺言公正証書の案を作成し、メール等により、それを当事者に提示します。 遺言者が、それを御覧になって、修正してほしい箇所を御指摘いただければ、公証人は、それに従って、遺言公正証書の案を修正します。 ◆遺言公正証書の作成日時の打合せと確定 遺言公正証書の案が確定した場合には、公証人は、遺言者が公証役場にお越しいただき、又は公証人が出張して、遺言公正証書を作成する日時について、当事者との間で打合せを行った上、確定します(事案によっては、遺言公正証書の作成日時が、最初に予定されることもあります。)。また、遺言公正証書の案が確定することによって、手数料の金額も確定するので、公証人は、当事者に対し、手数料の金額についても、事前にお知らせします。 ◆遺言公正証書の作成当日 作成当日には、遺言者本人から、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただき、公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上、前記4の確定した遺言公正証書の案に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。 |
内容に間違いがない場合には、遺言者及び証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります。
そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書は完成します。
作成当日に以上の手続を行うに当たっては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。
もっとも、御夫婦が同時に遺言公正証書を作成する場合には、御夫婦の間で互いにその内容について十分な話合いを行われていることなどから、御夫婦に御異存がないときは、例外的に、御夫婦が同席したまま、御夫婦の遺言公正証書を作成することもあります。
公正証書遺言の秘密保持とは?
公正証書遺言を遺言書として作成する背景には、公正証書遺言が遺言書として有効と判断されやすいことも一つの理由ですが、それだけではなく秘密保持に優れている点も公正証書遺言が評価される背景です。
公正証書遺言を作成する際に、立ち会いが必要になる公証人は、守秘義務が課されており、守秘義務違反をした際には法律で罰せられる対象です(公務員)。
証人も、公正証書遺言の内容を外部に漏らすことはなく、事前に証人に対して外部に公開しない旨に同意をもらうこともできます。
また、遺言公正証書自体も公証役場に厳重に保管されており、遺言がなくなるまで外部に遺言者の知らないところで公開されることはありません。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。