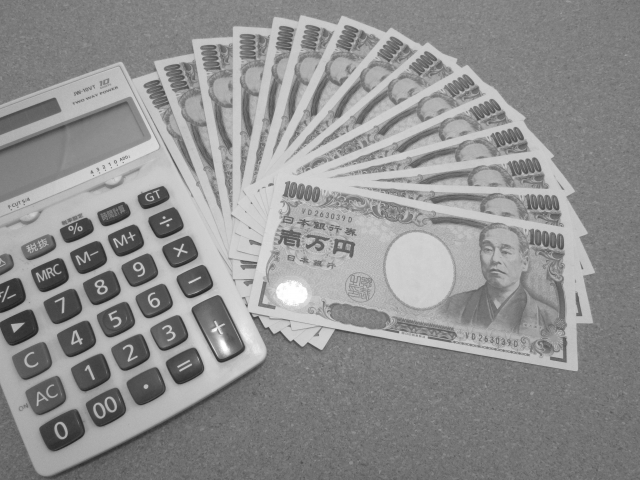遺族年金はいくらもらえるのかを知りたい人に向けて、遺族年金はいくらもらえるのか、中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは何かを紹介します。
遺族年金はいくらもらえる?
遺族年金の支給額は、被保険者の年金保険料納付期間や収入などによって異なります。
また、受給者の続柄によっても異なります。
配偶者の場合、被保険者が生前に支払った年金保険料に応じて年金額が決定され、具体的には、被保険者が60歳未満で死亡した場合、配偶者に対しては被保険者の年金保険料納付期間に応じて、月額70~90%程度の年金が支給されます。
遺族基礎年金の支給額
遺族基礎年金の支給額は、日本年金機構によると以下の通りです。
◆子のある配偶者が受け取るとき:777,800円+子の加算額
◆子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。):777,800円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額:各223,800円
- 3人目以降の子の加算額:各74,600円
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、日本年金機構によると以下の通りです。
| 遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。 |
遺族年金は、亡くなった人が加入していた社会保険によって、その遺族に支払われる年金です。
遺族年金の制度とは?
日本では、遺族年金は主に以下の3つの制度に分かれます。
- 厚生年金遺族基礎年金:厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支払われる年金です。被保険者が死亡した時点で、配偶者や子どもなどの遺族がいる場合に、支払われます。
- 公務員共済組合遺族年金:公務員共済組合に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支払われる年金です。被保険者が死亡した時点で、配偶者や子どもなどの遺族がいる場合に、支払われます。
- 国民年金遺族基礎年金:国民年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支払われる年金です。被保険者が死亡した時点で、配偶者や子どもなどの遺族がいる場合に、支払われます。
遺族年金の支払い額は、被保険者の加入期間や保険料納付状況、遺族の人数や年齢、配偶者かどうかなどによって異なります。
また、遺族年金は結婚している場合や、再婚した場合には支払いが停止されることがあります。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金について日本年金機構の説明は、以下の通りです。
遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
◆子のある配偶者
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金について日本年金機構の説明は、以下の通りです。
遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
- 妻(※1)
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
- 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは?
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算について日本年金機構の説明は、以下の通りです。
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、583,400円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
※2 「子」とは次の人に限ります。 - 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子
※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。
※4 平成19年3月31日以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は、上記1.と※3の「40歳」を「35歳」と読み替えてください。
経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。)
- 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるよう決められています。
遺族年金は別居時は支給されない?
遺族年金は、被保険者が死亡した場合に、配偶者や子供などの遺族に支給される年金です。
ただし、別居中の配偶者に対しては、遺族年金が支給されない場合があります。
別居中の配偶者に遺族年金が支給されない理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 配偶者との婚姻関係が継続していたかどうかによって異なる場合があるため
- 配偶者との別居期間が長期間にわたる場合、被保険者が死亡する前に離婚などで婚姻関係が解消された可能性があるため
- 別居中の配偶者に遺族年金を支給する場合、被保険者が生前に遺族年金を受給する意思表示をしていたかどうかが問題になるため、証明が必要となることがあるため
以上のような理由から、別居中の配偶者に対しては、遺族年金が支給されない場合があるこ
とがあります。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。