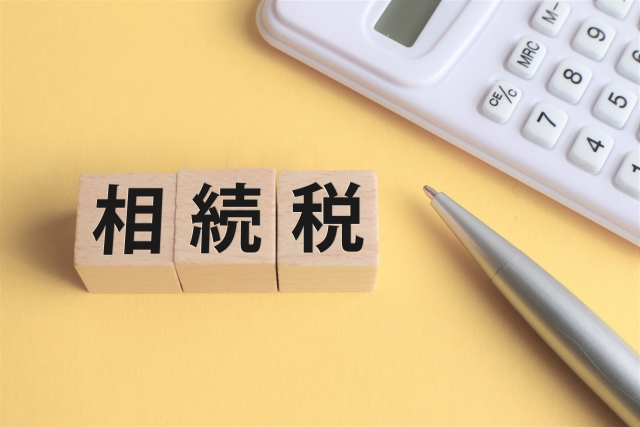遺産相続の税金について知りたい人に向けて、この記事では遺産相続の税金や遺産相続時の税金を支払う必要がある人、相続税の非課税枠について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続税とは?
相続税とは、日本国内にある資産を相続する場合に課税される税金です。
相続人が相続財産を受け取る際に、相続財産の価値に応じて納税する必要があります。
相続人には、配偶者や親族などの法定相続人がおり、彼らは相続税の基礎控除額を超える相続財産に対して、税率が適用されるのが特徴です。
基礎控除額は相続人の数によって異なりますが「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を満たす場合には、非課税になります。
遺産相続時の税金を支払う必要がある人とは?
遺産相続時に支払う必要がある税金は、相続税です。
そして、相続税は、相続財産を受け取る相続人が支払うことになります。
相続人には、配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。
ただし、相続人が相続財産を放棄する場合は、相続税も免除されます。
相続税の課税対象となる財産には、不動産、預金、株式、債券、現金などが含まれ、相続税の納付額は、相続財産の評価額に対して課税され、相続人ごとに相続財産の評価額から相続人控除額が差し引かれた金額に対して、相続税率が適用されます。
相続人が複数いる場合は、相続財産を分割して、それぞれの相続人の評価額と控除額を計算し、その合計額に対して相続税率を適用します。
相続税申告とは?
相続税申告とは、相続が発生した場合に、相続税を納めるために必要な手続きのことです。
相続税申告を行わなければ、相続税が納付されないため、重加算税や罰則金が課せられることになります。
相続税申告には、相続人や相続財産、評価額、相続税の計算方法などの詳細な情報が必要です。
また、相続人は相続発生から10ヶ月以内に相続税申告書を提出する必要があります。
ただし、提出期限を過ぎてしまった場合は、申告期限までに申告書を提出し、重加算税を納めることで申告が可能となります。
相続税申告書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能で、専門家に相談しながら作成することが望ましいです。
また、相続税に関する特別控除や税制優遇措置がある場合は、それに該当する書類を添付する必要があります。
相続税申告書が提出された後は、税務署が申告書を審査し、必要に応じて調査や指摘を行います。
その後、相続税の納税通知書が発行され、指定された期限内に相続税を納付することが必要です。
相続税率とは?
相続税率とは、相続税の納税額を決定するための税率のことです。
相続税率は、相続財産の価額や相続人の続柄などによって異なります。
また、相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に課税されるため、相続税率は相続人にとって非常に重要な要素となります。
現在の相続税の税率と控除額は、以下の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の非課税枠とは?
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額以下の場合に非課税になります。
この場合、相続税申告自体も必要ありません。
基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、法定相続人は民法が定める相続人です。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人が遺産分割の際に必ず受け取ることができる最低限の相続財産のことを指します。
遺留分は、亡くなった人が自由に遺産分割できる剰余財産のうち、法定相続人が相続分を受け取る前に、必ず分け与えなければならない財産として、民法によって定められています。
つまり、遺留分を確保している限り、遺言書などで自由に相続分配をすることができますが、遺留分を確保できない場合、法定相続人に対して、法律に定められた相続分を遵守しなければなりません。
遺留分は、配偶者や子供などの近親者に対して与えなければならない最低限の財産です。
遺留分が発生するケースとは?
遺留分は、以下のようなケースで発生します。
- 配偶者が相続人である場合:配偶者には、遺産の1/4が法定相続分として与えられます。この場合、配偶者に与えられる遺産の総額が法定相続分よりも少ない場合でも、遺留分が発生し、不足分が補填されます。
- 子が相続人である場合:子がいる場合は、子には遺産の1/2が法定相続分として与えられます。この場合、遺留分は発生しないことがありますが、子の法定相続分が不足している場合は、遺留分が発生し、不足分が補填されます。
- 子がいない場合:子がいない場合、遺産は配偶者に全て相続されます。この場合、配偶者には、遺産の3/4が法定相続分として与えられます。この場合でも、遺留分は発生し、遺産総額が法定相続分よりも少ない場合は、不足分が補填されます。
遺留分は、相続人の法定相続分が不足している場合に発生するため、遺言書などで相続人への分与を明示的に指定することが重要です。
遺留分と相続分の違いとは?
遺留分と相続分の違いは、相続人が相続財産を分ける際にそれぞれに与えられる権利の性質にあります。
相続分は、相続人が遺産を相続する権利のことで、法定相続人には法律に基づいて相続分が割り当てられます。
また、遺言によって指定された相続人にも相続分が割り当てられることも多いです。
相続分は相続人が相続財産を分ける際にそれぞれに与えられる割合です。
一方、遺留分は、相続人の中でも配偶者や子ども、父母など一定の身分に該当する相続人に対して、その相続分の一定割合以上を遺留者が遺贈できないように法律で保護された権利のことです。
つまり、遺留分は、法定相続分よりも優先的に保護されるもので、相続財産を分ける際に相続人が自由に分配できる範囲が制限されます。
遺留分は、遺言があっても侵されることはありません。
保険金の相続税とは?
保険金は、被保険者が死亡した場合、受取人に支払われる場合があります。
この場合、受取人は保険金を相続財産として申告することが必要です。
相続財産の総価額が相続税の課税対象となる基準額を超える場合、相続税が課税されることになります。
ただし、日本の相続税法には、「生命保険料控除」という制度があり、被保険者が死亡した場合に支払われる生命保険金については、相続税の対象外となる場合があります。
具体的には、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 被保険者が死亡した場合にのみ支払われる保険金であること
- 保険金の受取人が被保険者の配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹のいずれかであること
- 保険金の支払いが被保険者の死亡に直接関係すること
- 保険金の受取人が相続人であること
以上の条件を満たす場合、受取人は生命保険料控除を受けることができます。
ただし、生命保険料控除の上限額は、相続税法によって定められており、受け取る保険金額が上限額を超える場合は、超過分については相続税が課税されることになります。
遺産相続時の小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例は、国税庁によると以下の通りです。
| 個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。 |
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求について、裁判所によると以下の通りです。
| 遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。 |
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができなくなります。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、話合いを進めていきます。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。