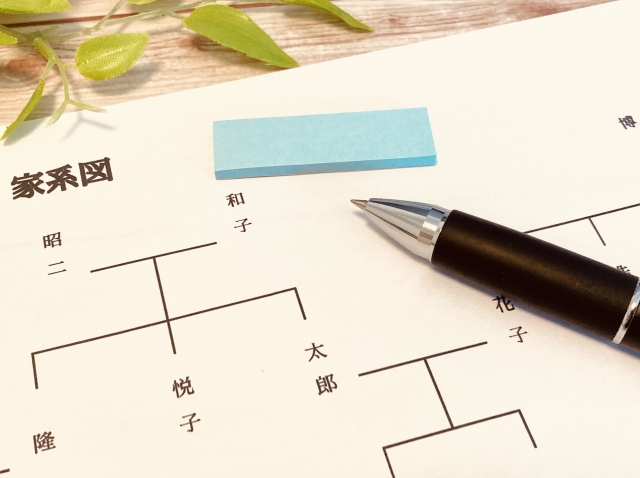遺産相続の順位について知りたい人に向けて、遺産相続の順位や子供がいない場合の相続人、遺言書を生前に作成した方がいいと言われる理由についても紹介します。
それでは、見ていきましょう。
配偶者は常に相続人になる
遺産相続において、配偶者は常に相続人になります。
これは、民法890条で「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」と定義されているためです。
配偶者以外の遺産相続の順位とは?
配偶者以外の遺産相続の順位は、以下のように決められています。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、法律によって定められている遺産分割方法になります。
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。
ただし、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではないのも特徴です。
法定相続分は、以下のように決められています。
- 配偶者と子供が相続人である場合:配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人である場合:配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合:配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
遺言書を生前に作成した方がいいと言われる理由
遺言書を生前に作成した方がいいと言われる理由は、以下の5つです。
- 相続人間で揉める機会を減らせる
- 遺産の分割方法を検討する時間をなくせる
- 遺産分割協議が不要
- 法定相続人以外にも相続できる
- 自分の意思で資産の相続ができる
相続人間で揉める機会を減らせる
遺言書を生前に作成した方が良い理由の一つに、相続人の間で揉める機会を減らせるということが挙げられます。
生前に自分の意思で遺言書を作成しておくことで、残された家族が相続で揉める機会を減らせるというのは大きな特徴でしょう。
いくら仲の良い家族であっても相続で金銭的なトラブルが発生し、疎遠になってしまうということもあります。
そのような事態を事前に回避できるという面でも、相続人間で揉める機会を減らすために遺言書を作成しておくのは有効な手段のひとつです。
遺産の分割方法を検討する時間をなくせる
遺言書を生前に作成した方が良い理由の一つに、相続人が遺産の分割方法を検討する時間をなくせるということが挙げられます。
被相続人が亡くなった場合、相続人がどのように遺産を相続するかを決める必要があります。
その際に、現預金だけではなく不動産などがある場合どのように分割するかが課題になることも多いです。
というのも、不動産などの場合すぐ現金化できない事も多く、すぐに現金化をすることで損をする可能性もあります。
一方で、不動産などの資産に関しても相続をする場合、分割をすることが求められます。
このような時に、事前にどのように遺産分割をするかを被相続人となる人が遺言書に記載しておけば、相続人として残された人たちの間で時間をかける事なく、遺産の分割を行うことが可能です。
遺産分割協議が不要
遺言書を生前に作成した方が良い理由の一つに、遺産分割協議が不要になるということが挙げられます。
遺産分割協議とは相続人とされる人が全て同意した上で、遺産分割の方法を明記したものになります。
遺産分割協議書を作成する際には、トラブルになることも多く時間がかかる可能性も高いです。
遺産分割協議書を作成することができない場合、遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停は以下の通りです。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このように時間がかかる可能性のある遺産分割協議を遺言書を作成しておくことで、なくせるというのは残された家族の時間を奪わないという面でも大きなメリットです。
法定相続人以外にも相続できる
遺言書を生前に作成した方が良い理由の一つに、法定相続人以外にも相続できるということが挙げられます。
遺言書を作成していない場合、相続は法定相続人に対して行われることになります。
そのため、自分が懇意にしている人や友達などに相続をしたい場合、生前に遺言書を作成していないと、相続できる可能性は限りなくゼロです。
このような背景から法定相続人以外にも相続したい場合は、遺言書を書くことは欠かせないと言えるでしょう。
自分の意思で資産の相続ができる
遺言書を生前に作成した方が良い理由の一つに、自分の意思で資産相続ができるということが挙げられます。
一般的に相続は遺言書を作成していない場合、自分の意思ではなく法定相続人が民法に沿って遺産を分割することになります。
もちろん、法律に沿って分割することでトラブルになる可能性は少ないですが、自分が多く資産を渡したいと思っている人に資産を残せないというのがデメリットです。
例えば、自分のことを懸命に介護してくれた長女に対して、より多くの遺産を残したいと思っていても、遺言書を作成していない場合、自分の子供であれば長女であろうが次女であろうが関係なく同じ金額が分配されることになります。
そのような背景から自分のことを世話してくれた子供に対して、より多く資産を残したいと思っている場合は、遺言書を作成しておくのが良いと言えるでしょう。
遺産相続で揉める原因とは?
遺産相続で揉める原因は、以下の通りです。
- 相続資産が少ない
- 結婚・離婚で相続人が多い
- 不動産など分割しにくい遺産が多い
- 相続人間でコミュニケーションが取れていない
相続資産が少ない
遺産相続で揉める原因の一つに、相続資産が少ないことが挙げられます。
相続資産が少ない場合、揉める機会が多いという統計も出ており、1千万円前後の場合、最も揉めるケースが多いとされています。
反対に、相続遺産が何十億円となっている場合、法定相続人が法律で決まった通りに分割をしても一人数億円もらえるケースが多く、被相続人の相続資産が莫大な場合、相続人も金銭的に余裕がある生活を送っている可能性が高いので、揉めるケースは少ないと言えるでしょう。
結婚・離婚で相続人が多い
遺産相続で揉める原因の一つに、結婚・離婚で相続人が多いことが挙げられます。
現在、結婚している奥さん以外にも過去に結婚しており、その人との間に子供がいる場合、その子供も相続人にあたります。
一方で、現在の奥さんとその家族にとって被相続人の前妻の子供は面識のない人であることが多く、そもそも現在のご家族が前妻との子供の存在を知らないケースもあります。
前妻との間の子供であれば法定相続人になる権利があり、かつ前妻との子供にとっては相続放棄する理由もないので、相続をするというケースが多いです。
このような場合に、現在の家族と前妻との子供間でトラブルになるケースもあります。
不動産など分割しにくい遺産が多い
遺産相続で揉める原因の一つに、不動産など分割しにくい遺産が多いことが挙げられます。
分割しにくい資産の場合、これらの遺産を分割するため現金化もしくは分割するための適正な方法を考える必要があります。
その過程の中でトラブルになるケースも多く、ご家族の中には現金化をして現金でもらいたいという人もいれば、土地などをそのまま残しておきたいという人もいます。
この結果、トラブルになってしまうケースも多いです。
相続人の間でコミュニケーションが取れていない
遺産相続で揉める原因の一つに、そもそも相続人の間でコミュニケーションが取れていないということが挙げられます。
家族仲が悪い場合、相続人の間でコミュニケーションを取ることができず、どのように遺産相続をするのかが明確にならないことも多いです。
そして、コミュニケーションが取れてない結果、分割案の合意を取ることもできず結果的に泥沼化してしまうこともあります。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。