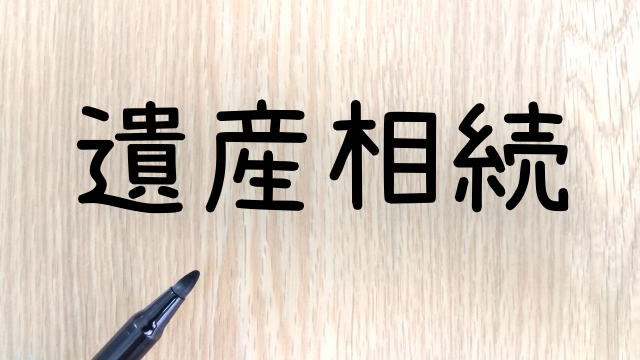遺産相続について詳しく知りたい人に向けて、この記事では遺産相続とはそもそもどのような制度なのか、遺産相続ができる人はどのような人なのか、遺産相続にかかる税金はいくらなのかについて詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺産相続とは?
遺産相続とは、亡くなった方の保有していた不動産や預金などの資産を相続人に相続することを指します。
遺産相続は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があり、相続ができるのは法定相続人です。
ただし、遺言書がある場合は法定相続人以外が相続をすることもできます。
また、遺産相続において重要なことの一つに相続放棄をせず遺産を相続する場合、プラス財産のみではなくマイナスの財産も相続をしなくてはいけないということです。
具体的に、プラス財産とマイナス財産には以下のようなものが挙げられます。
プラス財産
- 宅地
- 農地
- 山林
- 原野
- 牧場
- 池沼
- 鉱泉地
- 雑種地
- 戸建住宅
- 共同住宅
- マンション
- 店舗
- 工場
- 貸家
- 駐車場
- 現金
- 貸金庫
- 国債証券
- 社債
- 株式
- 手形
- 小切手
- 還付金債権
- 未収報酬債権
- 損害賠償請求権
- 慰謝料請求権
- 著作権
- 工業所有権
- 機械器具
- 農耕具
- 棚卸資産(商品、製品、原材料)
- 売掛債権
- 自動車
- 貴金属
- 絵画骨董品
- ゴルフ会員権
- 占有権
マイナス財産
- 住宅ローンの債務
- ローン
- クレジット残債務
- 賃借料
- 水道光熱費
- 通信費
- 管理費
- 敷金
- 補償金
- 預り金
- 買掛金
- 前受金
- 保証債務
- 連帯債務
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 固定資産税
- 土地計画税
- 相続税
- 贈与税
- 国民健康保険料
また、相続放棄をする場合はプラス財産・マイナス財産どちらも相続放棄をしなくてはいけません。
そのため、プラス財産のみを相続してマイナス財産は相続放棄をするということはできないので注意しましょう。
遺産相続できる人とは?
遺言書がない場合、法定相続人になれるのは配偶者と血族のみです。
また、法定相続人には順位があり、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。
そして、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の遺産相続の順位は国税庁より以下のように記載されています。
<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続人となる子供がすでに亡くなっている場合は、孫が祖父母も遺産を相続することが可能です。
孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥や姪が相続することになります。
遺産相続にかかる税金とは?
国税庁によると、遺産相続にかかる税金は以下のように計算するとされています。
- 「各人の課税価格の計算」で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
【各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額】 - 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
a.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
b.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。 - 上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
【課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)】 - 上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
【法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額】 - 上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
【各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額】
また、控除額は以下の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
課税価格から見る相続税早見表
課税価格から相続税を知る手段に、相続税早見表の利用が挙げられます。
相続税では、配偶者とそれ以外の法定相続人では控除額が大きく異なるため、相続税額も大きく変化するのが特徴です。
配偶者の場合は、配偶者の税額の軽減があり、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
ただし、配偶者の税額軽減は配偶者が遺産分割で得た財産をもとに遺産額を評価することになるので、相続税の申告期限までに遺産分割がされており、配偶者の遺産額が明確になっていることが必要です。
子供がいる場合は以下の通り、配偶者と控除額が異なるので、以下の早見表を参考にしましょう。
| 遺産評価額 | 子供1人の場合 | 子供2人の場合 | 子供3人の場合 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | – |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
| 3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
| 4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
相続税の控除額は、法定相続人の人数によって異なるので、子供が複数人いる方が相続税額は低くなるのが特徴です。
死亡保険の相続税はいくらまでなら不要?
死亡保険の場合、一定の金額まで相続税がかかりません。
これは、死亡保険金が被相続人の残された家族に対しての金銭的な援助という意味合いが強く、死亡保険が相続人の生活を保障するケースも多いためです。
相続人が、死亡保険を受け取る場合は、「500万円×法定相続人の人数」が非課税金額となります。
ただし、死亡保険金は必ず非課税になる訳ではなく、相続人と被相続人の関係や保険の種類によっても異なります。
非課税枠のある死亡保険金は、「被相続人が被保険者で保険料負担者、相続人が受取人」という関係の場合です。
また、相続人とは相続の資格がある法定相続人ではなく、相続をする相続人のことを指します。
そのため、相続放棄をした場合は相続人が受取人になっていても非課税枠の適用はありません。
そのほかにも、「契約上の受取人が被相続人だった生命保険金」である入院給付金・生存保険金・特約還付金も非課税枠の適用がありません。
遺産相続は税理士に相談した方がいい理由
遺産相続は税理士に相談した方がいい理由は、以下の3つです。
- 相続人の手間を省ける
- 相続について専門家に相談できる
- 相続税の申告ミスを減らせる
相続人の手間を省ける
遺産相続は税理士に相談した方が良い理由の一つに、相続人の手間を省けるということが挙げられます。
遺産相続が発生する場面では、相続以外にも被相続人の死亡手続きやその他関連する手続き、親族や被相続人の知り合いへの連絡など様々なことをしなくてはいけません。
相続人が一人の場合、相続の手続きに時間を使えないこともあります。
特に、相続人がサラリーマンとして日中に働いている場合、全てを自分で行うのは時間的に不可能なことも多いです。
その点、遺産相続を税理士に相談すれば税理士が遺産相続に関わる税金の手続きを代行してくれるので、時間を有効利用することもできます。
相続について専門家に相談できる
遺産相続は税理士に相談した方が良い理由の一つに、相続について専門家に相談できるということが挙げられます。
遺産相続では、様々な疑問点が生まれるでしょう。
そのような場面でも、身近に相談できる専門家がいれば、スムーズに遺産相続の手続きを進めることができます。
相続税の申告ミスを減らせる
遺産相続は税理士に相談した方が良い理由の一つに、相続税の申告ミスを減らせるということが挙げられます。
遺産相続を税理士に相談することで、税理士が代わりに相続税申告を行ってくれます。
そのため、相続税の申告ミスを減らすことが可能です。
相続税は申告ミスをすることで重加算税や過少申告加算税などがペナルティとして与えられます。
その他にも相続税の申告ミスをすることで税務調査の対象になることもあるでしょう。
その点でも、税理士に依頼して相続税申告の代行を依頼できることのメリットは大きいです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。