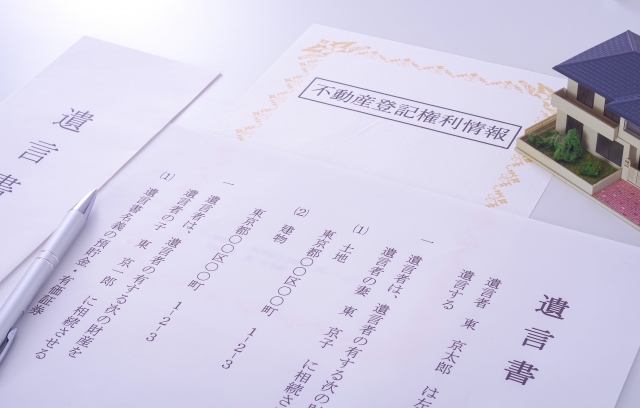遺言書の種類ごとに効力を発揮する基準について知りたい人に向けて、遺言書の効力について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺言書の種類
遺言書には、普通方式と特別方式と2つの方式があります。
また、遺言書は民法により書き方が決められていて、それに沿ったものではないと遺言書の効力がなくなってしまい無効です。
実際に、「民法第960条:遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない」と記載されています。
そして、遺言書が無効になってしまうケースは少なからず発生しています。
そのため、自分が残した大切な財産を希望通りに相続させるためにも、法律に沿った効力のある遺言書を作成することが大切です。
普通方式
一般的な遺言書は、この普通方式に当てはまります。普通方式には、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
特別方式
特別方式は、病気や事故などで死が迫っている場合、また乗った船が遭難した、伝染病などにより隔離された場所にいる、など特別な状況下にいる時に作成される遺言書です。
普通方式の手順を踏んでいたら間に合わない場合、特別方式によって遺言書を作成できます。
予め遺言書を作成する場合には、普通方式に則って作成をおこないます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名前の通り遺言を作成する本人が、全文を自筆で書く遺言書です。
思い立った時に作成ができ、また特別な費用もかからないため、3種類の中で1番手軽な方法ですが、自分で作成するため無効となる可能性も高いです。
自筆証書遺言として遺言書を残すためにはさまざまな作成要件が決められており、要件に沿ったものでない場合無効となってしまいます。
効力のある遺言書を作成するためにも、要件を満たしたものを作成することが必須です。
民法で定められている自筆証書遺言の作成要件
民法では、自筆証書遺言の要件として下記のとおり定められています。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む)の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(辞書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
- 自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
有効な自筆証書遺言を作成するためのポイント
有効な自筆証書遺言を作成するためのポイントは、以下の3つです。
- 遺言書の全文、記載した日付、氏名は全て自筆で書く
- 必ず押印をすること
- 遺言書の内容を訂正したら、必ず二重線を引き、訂正印を押す
遺言書の全文、記載した日付、氏名は全て自筆で書く
家族の代筆やパソコンなどで作成したものは効力が認められません。
ただし、相続財産の全部または一部の目録については、パソコンで作成したものや預金通帳などのコピーでも有効です。
その場合には、全ページに署名と押印が必要です。(両面コピーの場合には、その両面に署名と押印が必要。)
必ず押印をすること
遺言書に押印がないと無効になります。
印鑑の種類の指定はありませんが、実印が最適でしょう。
実印がない場合には認印でも大丈夫です。
シャチハタなど誰でも手に入るような印鑑は避けた方がいいです。
遺言書の内容を訂正したら、必ず二重線を引き、訂正印を押す
内容を訂正した場合、欄外に訂正した文字や変更した内容、署名が必要です。
例えば、遺言書の2項を変更した場合、欄外に「上記2中、3字削除、2字追加 山田 太郎」というように、訂正内容を自筆する必要があります。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、自筆で作成する自筆証書遺言は、紙とペンがあればいつでも書き記すことができることです。
また、誰にも知られずに作成することができるのも魅力でしょう。
自分で作成するメリットは、内容を誰にも知られずに作成できるところです。
知られたら反対意見が出る、自分が死ぬまでは遺言書の内容を知られたくない、など考えている人にはおすすめです。
そのほかにも法務局で保管してもらえるのも大きなメリットになります。
自筆証書遺言を自分で保管しておくと、なくしてしまったり、捨てられてしまったりするリスクが高くなります。
それを避けるため、法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらうことができます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、自分で作成するため、要件を満たしていないと遺言書の効力を失う可能性が高いところです。
自筆証書遺言を残す際には、民法で要件が事細かに決められています。
1つでも要件が欠けたものだと遺言書としての効力を失ってしまいます。
遺産が少ない場合であれば自分で作成することも可能ですが、株や土地など遺産が多岐に渡る場合には、自筆証書でも弁護士や司法書士など法律の専門家と相談しながら作成される方がほとんどです。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成します。
遺言者が自筆で記す自筆証書と大きく異なる点です。
また、公証人が作成することにより、遺言自体の信頼性が高まり強い効力を持ちます。
民法で定められている公正証書遺言作成の要件
民法では、公正証書遺言の要件として以下の6つが定められています。
- 証人2人以上の立会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること
- 公証人は、遺言者より口頭で伝えられた遺言の内容に基づいて遺言書を作成すること
- 作成した遺言書を遺言者、証人に読み聞かせる、または閲覧させて内容に間違いがないか確認すること
- 内容に間違いがないか確認したら、遺言書に証人と遺言者が署名、押印をすること
- 最後に公証人が遺言書に署名、押印をすること
公正証書は公証人によりこれらの要件を満たした遺言書が作成されます。
そのため、遺言書の効力・信頼性が高く、公正証書遺言が無効になるケースはほとんどありません。
確実に遺言を残したい人は、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
公正証書遺言を作成するためのポイント
公正証書遺言を作成するためのポイントは、以下の3つです。
- 事前に公証役場に持ち物を確認する
- 証人2人を用意する
- 遺産の配分などは予め決めておく
事前に公証役場に持ち物を確認する
公正証書遺言を作成する場合、戸籍謄本や印鑑証明書、また財産がわかる預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書など書類が複数必要になります。
必ず事前に公証役場に問い合わせて、どの書類が必要か確認しましょう。
証人2人を用意する
公正証書遺言には証人が2人必要です。
また、以下の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人
- 遺産を受ける人(受遺者)とその配偶者、子・孫・父母・祖父母などの直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、雇人
もし証人が見つからないようであれば、有料で公証役場にて紹介してもらったり、弁護士や司法書士などに証人を依頼したりすることも可能です。
遺産の配分などは予め決めておく
公証人はあくまでも遺言を遺言者の言われた通りに作成するのが仕事です。
そのため、遺産の配分や相続税などの相談はできません。
もし遺言書を残すにあたって迷っていることや知りたいことがあれば、予め弁護士や司法書士に相談しましょう。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するため強い効力を持つことです。
公正証書遺言には、公証人と証人が2人の合わせて3人が遺言書の作成の際に立ち会い、その内容に間違いがないか確認します。
そのため無効になるケースはほとんどありません。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかることです。
公正証書遺言を作成するには手数料がかかります。
手数料は遺産の額や遺言書の数によっても変わりますが、一般的に4〜10万円ほどです。
また、公証役場に足を運んだり、複数の書類を用意するなど手間がかかることもデメリットでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られたくない、秘密にしたい時に残す方法です。
ただし、デメリットの方が多く実際に秘密証書遺言はほとんど利用されていません。
秘密証書遺言は、遺言書の内容ではなく「遺言書がある」ということを、公証人と証人に証明してもらう方法です。
公証役場には作成済みの封をした遺言書を持参するため、公証人や証人に中身を知られることがありません。
また、秘密証書遺言として届け出た後、遺言書は自分自身で保管します。
公証役場では、あくまでも「遺言書が作成された」という記録が残ります。
そのため遺族は遺言者が亡くなった後で公証役場に確認して「遺言書があるかないか」を確認することができます。
秘密証書遺言の効力が弱いとされる理由
秘密証書遺言は、公証人などが中身を確認することができません。
また、自分が亡くなった後に開封されて、その遺言書が遺言書としての形式からはずれていた場合には、その遺言書は無効になってしまいます。
秘密証書遺言を作成したにもかかわらず、秘密証書遺言として認められないケースも多いです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。