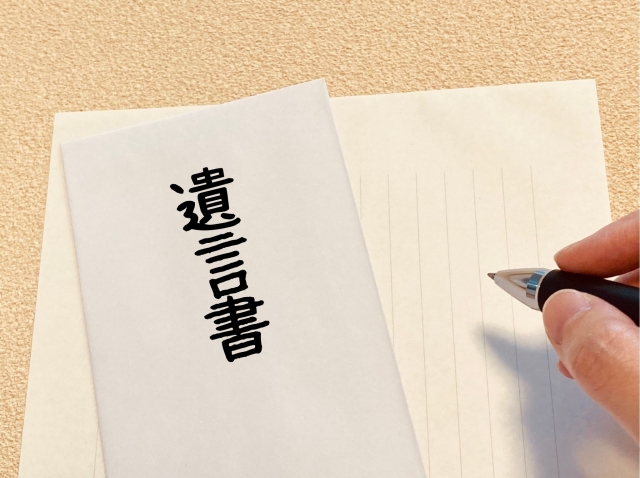遺言書の書き方について知りたい人に向けて、遺言書の書き方や種類、作成するメリット、遺言書に記載すべきことなどを紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺言書の種類と書き方
遺言書の種類と書き方は、以下の通りです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全てを自筆で執筆する遺言書です。
作成に費用や手間がかからないので、作成のハードルが低いのが特徴ですが、自筆証書遺言として認められるためにはいくつかの要件を満たす必要があり、一つでも満たしていない場合は、自筆証書遺言として認められないので注意が必要になります。
自筆証書遺言の作成では、まず遺言者がパソコンや代筆を使わず自筆で全てを書き上げることが求められます。
細かい要件としては、自筆証書遺言を執筆した日を年度も含めて記載することが必要で、訂正の際には、二重線で消し、印鑑を押すことが必要です。
また、自筆証書遺言の最後には自筆の署名と押印が必要になり、署名もしくは押印が抜けている場合は、自筆証書遺言として認められないので注意しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人の前で、遺言の内容を口頭で告げることで成立します。
自筆証書遺言と違い、自筆で遺言書を書き上げる必要がないので、障害などがあり自筆で遺言書を作成できない場合などに有効です。
また、公正証書遺言では公証人が、遺言者をサポートしつつ公正証書遺言を制作できるので、公正証書遺言の制作経験がない人やどのように遺言書を作成すればいいのかわからない人にも公正証書遺言はおすすめです。
公正証書遺言の作成では、遺言者はメールや手紙等の方法で公証人に自分が保有している資産や遺言書の内容を伝えます。
公証人は、遺言者からもらった情報をもとに遺言書を作成するので、遺言者は公証人が作成した公正証書遺言で問題ないかを確認して、修正箇所があれば指摘することが可能です。
ただし、公正証書遺言の場合はこれだけでは遺言書として認められず、公正証書遺言として正式に認められるためには遺言者本人が公証人と証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げて、判断能力を有する遺言者の真意であることを確認する必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、誰にも遺言書の内容を知られることなく遺言書を残せるのが特徴です。
一方で、相続人が秘密証書遺言の存在自体を知らないことも多く、死後に秘密証書遺言の存在を外部から伝えられることもないので、秘密証書遺言の存在を知らないまま遺産相続がなされてしまうケースもあります。
また、秘密証書遺言は全文自筆で執筆する必要はなく、パソコンで作成することも可能です。
秘密証書遺言の作成方法は、以下の通りです。
- 遺言者が遺言書を執筆する。その際に、秘密証書遺言に署名と押印を行う
- 遺言者自身が秘密証書遺言を封筒に入れ、証書に押印して封印する
- 秘密証書遺言を公証人役場に持って行き、公証人と証人2人の前で、秘密証書遺言の作成者が自分であることを証明する
- 公証人が秘密証書遺言の提出された日付と遺言者の申述を封紙に記載し、公証人が遺言者・証人とともに署名・押印する。
遺言書に記載すべきこととは?
遺言書に記載すべきことは、以下の5つです。
- 相続資産
- 遺産分割方法
- 相続をする人
- 遺言執行者
- 付言
相続資産
遺言書に記載すべき事項の一つに、相続資産が挙げられます。
相続資産を記載する目的は、被相続人となる遺言者がどのくらいに資産を持っているのかを事前に明確にすることです。
相続する資産のなかには、日本国内の財産のみではなく海外の財産も含まれます。
また、現預金だけではなく不動産や証券、株券なども含め全ての財産を記載しておく方が遺言書としての効力を持ちやすいです。
遺産分割方法
遺言書に記載すべき事項の一つに、遺産分割方法が挙げられます。
遺産分割方法は、自分が残した遺産をどのように分割するかを明記したものです。
遺産分割では、不動産などの有形資産をそのまま有形資産として相続するのか、現金化して相続して欲しいのかなど様々な要望があるでしょう。
このような要望を遺言書に記載しておくことで、残された相続人たちが揉めることなく相続をすることが可能になります。
相続をする人
遺言書に記載すべき事項の一つに、相続をする人が挙げられます。
相続をする人を記載していない場合、血縁者である法定相続人が相続人になります。
ただし、遺言書に相続して欲しい人を記載することで、法定相続人でない人に対しても自分の遺産を相続させることができます。
そのため、自分が日頃懇意にしている人がいる場合や生前お世話になった人に対して相続をしたいと思っている場合は、遺言書に相続人として記載をしておくことで相続することが可能です。
遺言執行者
遺言書に記載すべき事項の一つに、遺言執行者が挙げられます。
遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現する人のことです。
民法1012条1項では以下のように定義されています。
遺言執行者の権利義務:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
付言
遺言書に記載すべき事項の一つに、付言が挙げられます。
付言とは、遺言書に記載されているものも、記載されている事項自体に法的効力がない部分のことです。
葬儀・納骨に関する希望、感謝の言葉などが付言に当たります。
遺言書を作成するメリットとは?
遺言書を作成するメリットは、以下の5つです。
- 自分の意思で相続を決められる
- 法定相続人以外にも相続できる
- 相続人同士の争いを阻止できる
- 相続がスムーズにできる
- 遺産分割協議の手間を省ける
自分の意思で相続を決められる
遺言書を作成するメリットの一つに、自分の意思で相続を決められるということが挙げられます。
通常、相続は被相続人の死亡後に行われるものなので、被相続人となる人がどのように遺産を分割するか、どのように自分の遺産を相続人に分割するのかを決めることはできません。
ただし、遺言書を事前に作成しておくことで被相続人となる人が生存しているうちに、自分の意思で、遺産分割方法や誰にどのくらいの遺産を渡すのかを決めることができます。
このように、遺言書を作成することで自分の意思で決められるので、被相続人の意思を反映し、自由度高く遺産相続できるというのも大きな魅力でしょう。
法定相続人以外にも相続できる
遺言書を作成するメリットの一つに、法定相続人以外にも相続できるということが挙げられます。
遺言書を作成し相続人の欄に、法定相続人以外の名前を書くことで、法定相続人以外の人物に自分の遺産を相続させることが可能です。
そのため、結婚はしていないが事実婚状態の内縁の妻に自分の遺産を相続したい場合などには、遺言書を作成するのが有効になります。
それだけではなく、お世話になった人に対して少しでもいいから遺産を譲渡したいと思っている場合も遺言書を作成しておくことが有効です。
ただし、遺言書に法定相続人以外の名前を記載することで、法定相続人と遺言書に名前を書かれた相続人の間でトラブルが発生する可能性もあるので、遺言書に法定相続人以外の人の名前を記載する際には、事前に相手には相続人として遺言書に名前を記載したい旨をお伝えして問題ないかを確認しておくといいでしょう。
また、法定相続人にも相続人として法定相続人以外の人を指定したい旨を伝えることが必要です。
相続人同士の争いを阻止できる
遺言書を作成するメリットの一つに、相続人同士の争いを防止できるということが挙げられます。
遺言書を作成し、誰にどのくらい遺産分割するのかを明記することで、相続人同士の争いを阻止することができ、スムーズに遺産相続することが可能です。
例えば、兄弟が3人いて1人だけ海外の大学に留学し、被相続人となる人から多額の援助をもらっていた場合、被相続人の死後、相続人の間で留学費用を巡って遺産分割トラブルが発生する可能性も考えられます。
このような場合でも、遺言書を作成しておくことで留学費用の援助をもらっていない他の兄弟に対して、少しでも多く遺産を残すような分割を被相続人が指定することも可能です。
相続がスムーズにできる
遺言書を作成するメリットの一つに、相続がスムーズにできるということが挙げられます。
遺言書がない場合、相続人はまず法定相続人が誰になるのかを被相続人の戸籍謄本を調べた上で確認し、さらにどのくらいの遺産があるのかも登記簿などから確認する必要があります。
その点、遺言書があれば事前にどのくらいの資産があり、かつ誰に相続をするのかが明確になっているので、被相続人の資産の相続がスムーズにいく可能性が高く、調査に対して時間がかかる可能性も低いので、結果的に時間・金銭的コストを削減することが可能です。
遺産分割協議の手間を省ける
遺言書を作成するメリットの一つに、遺産分割協議の手間を省けるということが挙げられます。
遺産分割協議とは、被相続人の死後、相続人の間でどのように遺産分割をするのかを協議することを指します。
遺産分割協議は法定相続人となる全員の同意が必要です。
一方で、認知症を発症している高齢者がいる場合やまだ未成年の子どもがいる場合、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性も考えられます。
それだけではなく連絡がつかない相続人がいる場合は、遺産分割協議自体を開くことができず、遺産分割を期限までにできない可能性もあるでしょう。
その点からも遺言書を作成し、遺産分割協議の手間を省けるというのは大きなメリットです。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。