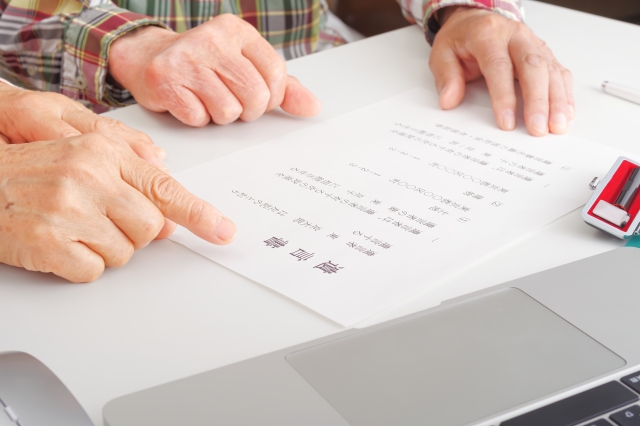遺言書を書きたい人に向けて、この記事では遺言書の書き方や遺言書を残すメリットを紹介します。
それでは、見ていきましょう。
遺言書の種類とは?
遺言書の種類は、以下の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、財産目録以外の部分をすべて手書きで記載しなくてはいけない遺言書です。
そのため、体力の衰えや障害などで字が書けない人の場合は、自筆証書遺言を利用することができません。
また、自筆証書遺言の作成時には公証人が不要ではありますが、公証人のチェックを受けた遺言書を作成することもできません。
そのため、自筆証書遺言は法律的に見て不備な内容になってしまうことや、自筆証書遺言の内容が法律的に不適格で相続人の間でトラブルになってしまう可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人と証人の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言者の意思として文章にしたものを指します。
公正証書遺言は、比較的安価に作成できるだけではなく、 裁判官や検察官、弁護士のような法律の知識・経験を持っている公証人に対して遺言書の内容を口頭で伝えることができるので、遺言者が法律を完全に理解していなくても公証人が遺言者の話す内容をまとめて法律的に問題がないような遺言書を作成してくれます。
このような背景から、公正証書遺言は最も安全な遺言書作成方法と言われています。
また、公正証書遺言の場合は口頭で内容を伝えれば公証人が遺言書にしてくれるだけではなく、公正証書遺言では遺言者の自筆署名が不要です。
そのため、体力が落ちている場合でも公正証書遺言は作成できます。
公正証書遺言の場合は、出張で作成することもできるので、自宅や老人ホーム、介護施設、などに公証人に来てもらった上で公正証書遺言を作成可能です。
そして、公正証書遺言は相続人にとってもメリットの大きい遺言書形式として知られています。
公正証書遺言は、原本だけではなく電子データにして、保管される仕組みが構築されています。そして、日本公証人連合会では遺言登録・検索システムを使って、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をそのシステム上で管理しているので、公正証書遺言の有無を相続人が調べることも可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、公証人及び証2名の前で封書することで有効になる遺言書の種類です。
秘密証書遺言は、全文を手書きで記載する必要はなく、パソコンで作成したものであっても秘密証書遺言として認められます。
一方で、秘密証書遺言の場合は公証人が秘密証書遺言の内容を確認することはないので、法律的に不備がある場合などでも、そのまま秘密証書遺言として保管されることになり、法律的観点から遺言書として認められないこともあります。
自筆証書遺言を書く際の必須事項とは?
自筆証書遺言を書く際の必須事項は、以下の5つです。
- 本人の手書き
- 宛先を明確にしている
- 記入日を明記する
- 署名・押印をする
- 誤字脱字をしない
自筆証書遺言を作成する際には、以下の条件を満たすことが正式に求められています。
- 第968条では、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
- 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
そこで、ここでは上記を踏まえた上で自筆証書遺言を書く際の必須事項について紹介します。
本人の手書き
自筆証書遺言を書く際の必須事項のひとつに、本人の手書きであるということが挙げられます。
自筆証書遺言書と名前があるように、自筆証書遺言書を作成する際には自分で全文を手書きで記載する必要が求められます。
そのため、パソコンで作成したものや音声を使った遺言書は、自筆証書遺言書としては認められていません。
宛先を明確にしている
自筆証書遺言を書く際の必須事項のひとつに、宛先を明確にすることが求められます。
自筆証書遺言には、推定相続人を記載することが求められており、推定相続人の記載がないものに関しては自筆証書遺言として認められていません。
また、推定相続人に相続させる場合には、「相続させる」もしくは「遺贈する」と記載することが必要です。
推定相続人に財産を「相続させる」旨の遺言をする場合は、遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に記載する必要はありませんが、推定相続人に財産を「遺贈する」場合は、遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に受遺者として記載する必要があります。
また、推定相続人以外に遺産相続する場合は、「遺贈する」と記載する必要があります。
記入日を明記する
自筆証書遺言を書く際の必須事項のひとつに、記入日を明記することが挙げられます。
自筆証書遺言に記載する記入日は、自筆証書遺言を作成した年月日を記載することを指しており、「年/月/日」の形式で具体的な年月日まで記載することが必要です。
署名・押印をする
自筆証書遺言を書く際の必須事項のひとつに、被相続人の署名・押印をすることが挙げられます。
自筆証書遺言に記載する署名・押印は、戸籍どおり(公的機関への書類記入)の氏名をを記載する必要があります。
そのため、ペンネーム等で自筆証書遺言を作成すると自筆証書遺言として認められない場合もあります。
誤字脱字をしない
自筆証書遺言を書く際の必須事項のひとつに、自筆証書遺言を作成する際に誤字脱字をしないということが挙げられます。
自筆証書遺言を作成する際には、誤字脱字をしないようにし、誤字脱字をした場合は書き直すことが推奨されます。
これは、誤字脱字があることで自筆証書遺言としての効力が発揮されないことや、意図しない解釈をされる可能性があるためです。
ただし、自筆証書遺言の作成において誤字脱字が発生し書き直しも難しい場合は、誤字脱字箇所を明記し、変更・追加の旨を付記して署名・押印をすることで訂正として認識されます。
遺言書を作成するメリットとは?
遺言書を作成するメリットは、以下の5つです。
- 相続で揉める機会を減らせる
- 遺産分割協議の手間を省ける
- 法定相続人以外にも相続できる
- 生前に相続の意思を確認できる
- スムーズに相続できる
相続で揉める機会を減らせる
遺言書を作成するメリットの一つに、相続で揉める機会を減らせるということが挙げられます。
特に莫大な資産を持っている人の場合、残された相続人の間でトラブルが発生する可能性も高いです。
そのようなトラブルを事前に避けるような目的でも、相続に関して事前に遺言書を作成しておくのは有効でしょう。
公的に認められた遺言書の場合、遺言書に従って資産が分配されることになるので、相続人の間でトラブルを避けることができます。
遺産分割協議の手間を省ける
遺言書を作成するメリットの一つに、遺産分割協議の手間が省けるということが挙げられます。
仮に遺言書を残さないまま亡くなった場合、残された相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は全ての相続人が参加をすることが求められます。
そのため、家族が認知していない隠し子がいた場合や結婚・離婚を繰り返しており相続人がどこにいるか不明確な場合、遺産分割協議に手間がかかる可能性も高いです。
この点でも、事前に遺言書を作成しておくと遺産分割協議の手間を省くことができ、スムーズに相続人が遺産を相続することができます。
法定相続人以外にも相続できる
遺言書を作成するメリットの一つに、法定相続人以外にも相続できるということが挙げられます。
遺言書は法定相続人がどのように資産を相続するかを記載するだけではなく、自分が懇意にしている人に対して、自分が亡くなった後の資産を管理してほしいなどの遺言を残すことも可能です。
このように法定相続人以外にも自分の意志で、自分の亡くなった後の資産を託せるというのは、遺言書を作成するメリットの一つでしょう。
生前に相続の意思を確認できる
遺言書を作成するメリットの一つに、生前に相続の意思を確認できるということも挙げられます。
遺言書を作成することで、死後の資産をどのように相続するかを事前に考えることができ、家族を含めどのように自分が亡くなった後の資産を相続していけばいいかを考える機会にもなります。
スムーズに相続できる
遺言書を作成するメリットの一つに、スムーズに相続できるということが挙げられます。
相続で遺言書がない場合、場合によっては相続をするまでに数年間かかることもあります。
そのため、遺言書を事前に作成しておき、遺言書通りに相続人が遺産を相続できるというのはスムーズに相続人に資産を相続をする上でも重要なことでしょう。
まとめ
遺言書は、自分の状態に合わせたものを選択することが必要です。
また、相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。