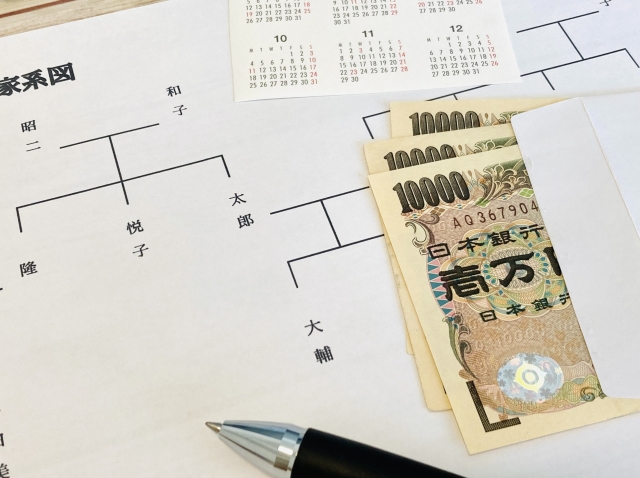法定相続分について詳しく知りたい人に向けて、法定相続分や法定相続人、法定相続分の計算方法について詳しく紹介します。
それでは、見ていきましょう。
法定相続分とは?
法定相続分とは、ある人が死亡した際に、その人の財産を分割する際に適用される法律上のルールのことを指します。
つまり、遺言がない場合や遺言で相続分を超える遺贈を受けた場合に、相続人が受け取ることができる最低限の財産の割合を決める基準となります。
法定相続人とは?
法定相続人は、国税庁によると以下の通りです。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
- 第1順位:死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続分の計算方法
法定相続分の計算方法は、国税庁によると次のとおりです。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
- 配偶者と子供が相続人である場合:配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続人である場合:配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合:配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
相続財産とは?
相続財産とは、ある人が死亡した際に、その人が所有していた財産全てを指します。
具体的には、以下のようなものが相続財産に含まれます。
- 不動産:土地、建物、マンション、戸建住宅など。
- 動産:預貯金、株式、債権、債務、車、家具、家電製品、衣服、貴金属、美術品、蔵書など。
- 知的財産権:特許権、商標権、著作権、肖像権、特許出願権など。
- 企業持分:株式や社債、信託受益権などを持つ場合、その所有権が相続財産となります。
- 生命保険金:被保険者が死亡した場合に、受取人に支払われる保険金が相続財産となります。
相続財産は、遺言がある場合や相続人間で協議をして分割する場合には、その分割方法が決められます。
しかし、遺言がない場合や相続人間での合意がない場合には、法定相続分に基づいて分割されることになります。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人同士が相続財産の分割方法について合意した内容を文書化したものです。
遺産分割協議書は、相続財産を公平かつ円満に分割するために重要な役割を果たします。
遺産分割協議書には、以下のような内容が含まれます。
- 相続財産の目録:相続財産の種類や量、評価額などが明記されます。
- 分割方法:相続財産をどのように分割するかについて合意された内容が記載されます。例えば、現金や預貯金は等分割、不動産は競売による売却後の分割、株式は株価に基づく分割など、財産ごとに適切な分割方法が決められます。
- 分割の割合:相続人ごとにどの程度の割合で分割するかが記載されます。法定相続分を尊重しながら、相続人間で合意された割合が反映されます。
- 財産管理に関する取り決め:相続財産の管理方法について合意された内容が記載されます。例えば、相続財産の売却や処分に関するルールや、相続財産の共同管理方法についての取り決めが含まれます。
- 署名と日付:相続人全員の署名と日付が必要です。
遺産分割協議書は、裁判所に提出することで正式な文書となります。
相続人同士が円満に相続財産を分割するために、遺産分割協議書を作成することは重要です。
ただし、相続人間の協議が難航する場合や、法定相続分を守らないような内容の協議書は、後々のトラブルを招くことになるため、注意が必要になります。
相続税とは?
相続税とは、相続によって発生する税金のことです。
相続財産の価値に応じて課税され、相続人が負担することになります。
相続税の課税対象となる相続財産の額は、相続人ごとに異なります。
また、相続人間の続柄や法定相続分に応じて、相続税の税率や非課税限度額も変わります。
具体的には、配偶者や直系卑属(子ども、両親、祖父母など)の場合は、非課税限度額が高く設定され、税率も比較的低いため、相続税の負担は軽減されます。
一方、兄弟姉妹や叔父叔母などの場合は、非課税限度額が低く設定され、税率も高めに設定されているため、相続税の負担が重くなるのが特徴です。
相続税の申告期限は、相続発生日から10か月以内とされています。
相続人は、この期限内に相続税の申告書を提出することが義務付けられています。
また、相続人が相続税の納税義務を負っている場合には、相続人が相続財産を分割する前に、相続税の納付義務があるかどうかを確認することが重要です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取ることを放棄することを指します。
相続放棄により、相続人は相続財産に対する権利や義務を放棄し、相続税の納付義務からも解放されます。
相続放棄の理由としては、相続財産が多額で相続税が負担できない場合や、相続財産に関する問題があり、それを解決することが困難な場合、相続人の個人的事情により相続財産を受け取ることが望ましくない場合などが挙げられます。
相続放棄は、相続人が相続財産を受け取る前に行うことが必要です。
相続放棄には、相続人が裁判所に申し立てる方法と、役所に届け出る方法があります。
また、相続放棄を行う際には、法定相続人の順位が変わることに注意が必要です。
例えば、長男が相続放棄を行った場合、その次に順位が下がる次男が相続人となる可能性があります。
争族とは?
「争族(そうぞく)」とは、相続人同士の間で相続財産を巡って発生する紛争や争いのことを指します。
相続人が多数いたり、相続財産が膨大な場合には、争族が発生しやすくなります。
また、相続人同士の人間関係が悪かったり、相続人の中に未成年者がいる場合にも、争族が発生する可能性が高いです。
争族が発生した場合、相続財産の分割や財産の処分方法、相続人間の権利や義務などについて、法律や裁判所の判断が必要となります。
そのため、争族は長期化する場合があり、相続財産が減少したり、相続人同士の関係が悪化することもあるため、できるだけ争いを避けるためにも、相続時には適切な準備を行うことが重要です。
弁護士に相談するメリットとは?
弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
- 正確なアドバイスがもらえる
- 相続手続きの手続きがスムーズに進む
- 相続税の節税対策が可能
- 相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる
正確なアドバイスがもらえる
法定相続分について弁護士に相談するメリットの一つに、正確なアドバイスをもらえることが挙げられます。
税理士は、相続税申告など相続税そのものについては詳しく理解をしていますが、法定相続分など相続税の背景にある法律的な観点については、弁護士と比較すると知識・経験が浅いです。
その点、弁護士であれば専門家として法律を学んでいるので専門的なアドバイスをもらえるだけではなく、具体的にどのように行動すればいいかまでの指針をくれます。
正確なアドバイスをもらうことができるので、結果的に後々トラブルになる可能性も小さく、法定相続分の取り扱いについてスムーズに決定できる可能性が高いです。
相続手続きの手続きがスムーズに進む
法定相続分について弁護士に相談するメリットの一つに、相続手続きがスムーズに進むことが挙げられます。
法定相続分について親族間で争いが発生している場合、弁護士に仲介を依頼することで、弁護士がスムーズに解決してくれます。
もちろん、親族間での話し合いで解決できる場合はそれが最善ではありますが、法定相続分の取扱いについて被相続人が再婚をしており、被相続人と前妻・前夫との間の子供と現在の妻・夫との間で直接的なコミュニケーションが難しい場合、弁護士に依頼をすることで相続手続きをスムーズに進目られる可能性が高いです。
相続税の節税対策が可能
法定相続分について弁護士に相談するメリットの一つに、相続税の節税対策が可能ということが挙げられます。
相続税に強い弁護士であれば相続税をどのようにすれば節税することができるのかの知識や経験が豊富です。
また、弁護士の場合は法律的には問題がない方法を提示してくれるのも大きな魅力です。
相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる
法定相続分について弁護士に相談するメリットの一つに、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができるということが挙げられます。
法定相続分がトラブルになる背景の一つに、被相続人が亡くなる間際に夫や妻と婚姻関係を結んだ場合が挙げられます。
この場合、被相続人の前妻や前夫との間に子供がいた場合、子供が現在の妻や夫に対して遺産相続させない姿勢を見せることもあります。
その点、被相続人となる人が生きているうちに弁護士に相談をすることができれば、どのようにすれば相続人間でトラブルが発生しにくいのか、また結婚をしていない状態であっても事実婚状態にある妻や夫に対して遺産を残す方法があるのかなども含め提案してもらうことが可能です。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
相続税の申告・生前対策のご相談なら相続特化の提案型税理士事務所である「アスク税理士事務所」にご相談ください。